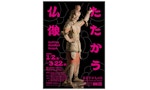第1章 みなとが、ひらく前
第1章は、「横浜の歴史は開港に始まる。それ以前は小さな漁村に過ぎなかった」という、横浜についての決まり文句を再考するセクション。横浜市歴史博物館の協力のもと、《人面付土器》(鶴見区上台遺跡)をはじめ、縄文期から広義の横浜市域に暮らしてきた人びとがつかったモノ、遺したモノが、「女性」「子ども」などのテーマに沿って紹介される。

第2章 みなとを、ひらけ
横浜が開港したのは1859年。当時の様子は、現在のみなとみらい線日本大通り駅付近に上陸したペリーの様子を描いた、ペーター・ベルンハルト・ヴィルヘルム・ハイネ(伝)《ペルリ提督横浜上陸の図》(1854以降)からうかがうことができる。
また横浜の西洋風の街並みや各国人の姿、鉄道などの風物は、錦絵となって流通した。昇斎一景《汐留より蒸気車通行の図》(1872)はその一例だ。


またこの章では、開港直後に始まる横浜の遊廓を描いた歌川芳員や歌川貞秀らの作品、さらには遊女の手紙などが紹介されている。外から入ってくる人びとを受け入れるため、まず遊廓や赤線を設けられた横浜。この構造は、その後も横浜にかたちを変えて残り続けることになる。