
第35回
[ARTIST IN FOCUS]MES×小宮りさ麻吏奈:領域横断的な活動を通じ、目の前にある「隔たり」に抗い続ける
2025年7月、東京都内で2つの個展──MES「カイ/KA-I」と小宮りさ麻吏奈「CLEAN LIFE/クリーン・ライフ」が開催された。新井健と谷川果菜絵によるMESはクラブカルチャー、小宮は漫画と、アートの外側の場でも活動している2組。今回の個展では、それぞれ養豚場と培養肉という主題を扱っており、対談からは共通する問題意識が浮かび上がってきた。

第35回
2025年7月、東京都内で2つの個展──MES「カイ/KA-I」と小宮りさ麻吏奈「CLEAN LIFE/クリーン・ライフ」が開催された。新井健と谷川果菜絵によるMESはクラブカルチャー、小宮は漫画と、アートの外側の場でも活動している2組。今回の個展では、それぞれ養豚場と培養肉という主題を扱っており、対談からは共通する問題意識が浮かび上がってきた。
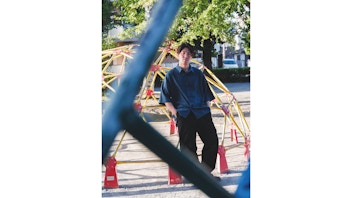
第34回
デジタルテクノロジーにより身体そのものの仮想化が進む現在、変容する身体観やアイデンティティを探求する、平田尚也。資生堂ギャラリーでの個展では、ネット上のパブリックデータを使い構成したデータを、映像や立体、平面作品と様々な出力で展開した。VRChatで普段から交流する彫刻家・西尾康之と変わりゆく私たちの存在について語った。

第1回
アートとデジタルテクノロジーによる創造拠点「シビック・クリエイティブ・ベース東京(CCBT)」が、渋谷から原宿へと拠点を移す。新しいスペースでこけら落とし個展をおこなうのは、CCBTが展開してきたコア・プログラム「アート・インキュベーション・プログラム」の2022年度アーティスト・フェローであるSIDE COREだ。メンバーである松下徹、高須咲恵、西広太志、播本和宜が個展の内容とCCBTとのつながり、今後への期待までを語ってくれた。

第3回
ミュージアムによるファンドレイジングの「いま」を追うシリーズ「美術館ファンドレイジング最前線」。第3回は、国内における寄付の現状と専門人材のファンドレイザーの役割を掘り下げる。社会課題の解決に取り組むクラウドファンディングのプラットフォーム「READYFOR」文化部門の責任者に現状を聞いた。

第12回
一般の人々が日常の暮らしのなかで生み出し、使い続けてきた「民具」。一見ただの古い道具に見えるかもしれませんが、様々な切り口から観察してみることで、ユニークな造形や意外な機能性といった「デザインの工夫」に気がつくことができます。第12回目は「午年と馬の民具」。これなーんだ?

第30回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は朝鮮美術文化研究・古川美佳のテキストをお届けする。

第29回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は塚田優(評論家)のセレクトをお届けする。

第28回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は金澤韻(現代美術キュレーター)のセレクトをお届けする。

第27回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は渋革まろん(批評家)のセレクトをお届けする。

第34回
美術館の学芸員(キュレーター)が、自身の手がけた展覧会について語る「Curator's Voice」。第33回は、東京・上野の東京都美術館で開催中の上野アーティストプロジェクト2025「刺繍―針がすくいだす世界」(〜2026年1月8日)を取り上げる。公募型展覧会で活躍する作家たちの取り組みを紹介するこのプロジェクトにおいて、「刺繍」と呼ばれる造形はどのように広がりを見せ、評価されてきたのだろうか。また、そこに感じられた違和感とはどのようなものだったのか。担当学芸員の大内曜が、本展の意義とともに語る。

第26回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は筒井宏樹(現代美術史研究)のセレクトをお届けする。

第25回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は、キュレーション/批評の畠中実によるテキストをお届けする。

第24回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は川北裕子(パナソニック汐留美術館学芸員)のセレクトをお届けする。

第23回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は石橋財団アーティゾン美術館学芸員・内海潤也のテキストをお届けする。

第22回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は、東京都写真美術館 学芸員の山田裕理によるテキストをお届けする。

第21回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は黒嵜想(批評家)のテキストをお届けする。

第20回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は、山口情報芸術センター[YCAM]キュレーターの見留さやかによるテキストをお届けする。

第19回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は塚田萌菜美(アートコンサルタント、アドバイザー)のテキストをお届けする。

第18回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回はキュレーター、東北芸術工科大学准教授の小金沢智のテキストをお届けする。

第17回
数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は学芸員資格を有し、美術館と数々のコラボレーションをしてきたhololive DEV_IS(ホロライブデバイス)所属のVTuber・儒烏風亭らでんのテキストをお届けする。