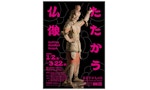「テクノロジーが描く風景―地質学的時間から果てしない未来へ」
3つ目のセクション「テクノロジーが描く風景―地質学的時間から果てしない未来へ」では、テクノロジーが与える影響を、地球規模にまで広げて考える。
まずは、シュウ・ジャウェイの映像作品《シリコン・セレナーデ》が展示されている。映画と現代美術の領域を往来する作品を制作してきたシュウは、現代のデジタル社会に欠かせない半導体のウェハー用シリコンが砂浜から採取できることに着目し、海辺、チェロの演奏シーン、AIチップの研究所などの映像を、自動生成された音楽とともに構成。半導体の世界的産地である台湾出身の作家が、砂浜という地球の土地とデジタル世界をつなぐ。

2025年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館展示の出品作家である藤倉麻子は、自身が幼少期に過ごした都市近郊の高速道路をはじめとするインフラの持つ機能と動態に興味を持ち、3DCGの映像を制作してきた。AI技術が大量の電力を必要とすることが指摘されているなか、藤倉は原子力発電施設や核燃料リサイクル施設を擁する下北半島をリサーチしたうえで、《インタクト・トラッカー》と構造物を制作。デジタル技術とインフラの分かち難い関係性を可視化した。


ヤコブ・クスク・ステンセンは、デス・バレーやモハーヴェ砂漠でのフィールドワークを通して、風景や動植物の写真、3Dスキャン、標本、録音データなどを収集。これらをデジタル化して融合することで、ドイツのロマン主義画家、カスパー・ダーヴィト・フリードリヒの作品に触発された、仮想の湖とそれを取り巻く生態系を創出した。誰もが美しく壮麗だと感じるロマン主義風景をつくりあげるとともに、一方的ではない双方向的な風景のあり方を提示している。

アニカ・イは、長年にわたり蓄積してきたイメージと、自身の初期作品データを用いて、生成AIによる「絵画」をつくりだした。完成した絵画は複数のレイターが動的な感覚を生み出し、絵画のあり方に疑問を投げかける。また、原生生物である放散虫をモチーフにした立体作品も同時に展示することで、生体的な芸術の可能性を問うている。

そしてアドリアン・ビシャル・ロハスは、アルゴリズムの処理による生成AIを基盤とするソフトウェア「タイムエンジン」を使って制作した彫刻シリーズ「想像力の終焉」を出展。デジタル上でシミュレーションされた環境に様々な条件を与えて生まれたこのモデルは、人間のあずかり知らぬ、まさに人類滅亡後の生物のイメージを喚起する。