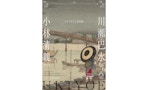人々の生活に深く根付いている「お弁当」は、行楽地での食事から日常生活にいたるまで、人のつながりを深めるソーシャル・ツールとしての役割を担ってきた。そんな「お弁当」を起点とするコミュニケーションを「食べることを巡るコミュニケーション・デザイン」としてとらえ、そこに焦点を当てた展覧会「BENTO おべんとう展―食べる・集う・つながるデザイン」が東京都美術館で開幕した。

小倉ヒラクによるお弁当をテーマにした新作アニメーションと、それにあわせたGOING UNDER GROUNDの松本素生による軽やかな歌声に誘われて展示室に向かうと、来館者を出迎えるのは江戸時代のお弁当箱だ。

お辨當箱博物館、北区飛鳥山博物館、新宿歴史博物館、そして国立民族学博物館といった館が所蔵する個性豊かな様々なお弁当箱。その凝った意匠を楽しみながら、各時代、各地域において人々が楽しくお弁当を囲んでいたその背景を想像することができる。
また、展示室内には実際にお弁当箱を触ることができるコーナーも設けられているので、直接手に取ることで、日本各地、そして世界各国のお弁当文化に触れてほしい。

同展示室内では、NHKの番組『サラメシ』で知られる写真家・阿部了による写真作品《ひるけ》(2018)にも注目したい。市井の人々が楽しそうに、ときに疲れた表情を見せながら頬張るお昼ご飯のお弁当。日常生活に優しく寄り添うお弁当の存在は、被写体たちのごく個人的な食事でありながら、鑑賞者たちにとっても身近に感じられる作品だ。

また、料理家・大塩あゆ美の《あゆみ食堂のお弁当》(2018)では、大切な人へのお弁当の写真とそのエピソードが綴られる。それぞれのお弁当がつくられた背景を読みながら、自分が食べてきた、あるいはつくってきたお弁当のことを思い出せるのではないだろうか。

次の展示室に向かうと、多くの細い布でできたリボンが目を引く。オランダの作家マライエ・フォーゲルサングのインスタレーション《intangible bento》(2018)だ。この作品では物語を聞くことが作品の一部になっている。
物語が聞こえる「精霊フォン」を耳にあてると、聞こえてくるのは「お弁当の精霊」の囁き。空間全体がお弁当箱のように見立てられており、リボンをくぐってお弁当箱の中に入ってみると、お弁当の精霊からの言葉を聞ける。次のリボンの先には何があるのか? なかには彫刻作品や参加型の作品など様々な作品があるので、宝探しのような気持ちでお弁当の精霊との対話を楽しみたい。

次の階に進むと、にぎやかな市場のような世界が広がっている。北澤潤の《FRAGMENTS PASSAGE ―おすそわけ横丁》(2018)だ。ここではお弁当を分け合う「おすそわけ」がつくり出すゆるやかなつながりに着目。様々な人から「おすそわけ」されたものが集まった「おすそわけ横丁」という実験的空間をつくり、参加者自身が、自分のものを他者と分け合う「おすそわけ」の意味を考えることを促している。
奥のスペースでは「おすそわけ」されたものを使った箸袋つくり体験やネックレスづくりなどのワークショップも行っている。なお、展示スペースの最奥には北澤の作品制作の過程を記したノートがあるので、そちらもあわせて注目したい。

最後の展示室には、可愛らしいお弁当箱の写真とともに、学校の教室のような机と椅子が展示されている。小山田徹の《お父ちゃん弁当》(2017)と森内康博の《Making of BENTO》(2018)だ。
小山田の作品は家族とのお弁当づくりのアーカイブともいえる作品。娘が描いたお弁当の指示書にあわせて、実際につくったお弁当の写真が展示されている。親子の信頼関係とともに、女の子の自由な想像力と小山田の実行力に驚かされる。

森内の作品は、お弁当をつくり慣れていない中学生たちが主役の映像作品が、大人にとっては懐かしい気持ちになるようなお弁当箱の中で上映されている。お弁当をめぐるフィクションとドキュメンタリーの映像6作品はどれも微笑ましい気持ちになりながらも、お弁当をつくるときに見えてくる、暮らしにおけるクリエイティビティに気付かせてくれるだろう。なお、展示室内には大きなお弁当箱に見立てたモニターにて、中学生たちの映像制作の様子を追ったドキュメンタリーも上映されている。

コミュニケーション・ツールとして、いつも人々のそばに寄り添ってきたお弁当。この展覧会では、そんな日常のなかの当たり前の存在に改めて気付かされるとともに、食べることにまつわるコミュニケーションの豊かさや複雑さに思いを馳せることができる。
なお、展覧会会期中はイベントも多数予定されているので、こちらもあわせてチェックしたい。