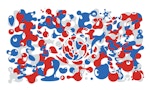1883年、モネは終の住処となるジヴェルニーに移り住んだ。1893年には邸宅南側の土地を買い足し、池を中心とした庭づくりを進めていく。池を描き始めるのは1895年頃だが、ここで始まったのは、たんに自然を写し取る風景画ではない。自ら設計し、整えた庭という「つくられた自然」を描く、新たな創作の段階であった。

ジヴェルニーの庭は、花々の配色や緻密に考えられた配置、池の造成に至るまで、自然に秩序を与える空間でもあった。1911年に妻アリスを、14年には息子ジャンを失うという深い悲しみを経験したのち、モネは再び制作に向き合い、より大きな仕事を成し遂げたいという思いのもと、《睡蓮》の大作に取り組んでいく。完成した作品群は、第一次世界大戦の休戦を記念して国に寄贈され、モネの没後、1927年にオランジュリー美術館に収蔵された。

セクション11では、様々に展開した《睡蓮》の作品が紹介されるとともに、同時代に同じ主題を工芸で表現しようとしたエミール・ガレやドーム兄弟によるアール・ヌーヴォーの作品もあわせて展示。絵画と工芸、平面と立体、自然と装飾が交差し、ジヴェルニーの水面は「風景」であると同時に、視覚表現の実験の場として立ち現れる。

本展の特徴のひとつは、絵画史の文脈に「写真」という視覚メディアを組み込み、モネの風景表現の変化を照らし出している点にある。写真室1(セクション2「モティーフと効果」)では、19世紀に画家たちが戸外制作を始めたのと同時期、写真家たちも森や郊外を制作の場とし、自然と向き合っていった流れが紹介される。

写真室2(セクション9「効果と反射」)では、19世紀末に写真家たちがたんなる再現から離れ、より内面的な表現として風景を捉え始めた動向に注目する。写真室3(セクション10「ジヴェルニーの庭のクロード・モネ」)では、通産大臣でもあったエティエンヌ・クレメンテルが撮影した、カラー写真・オートクロームが紹介される。
展覧会の終章を飾るのが、現代作家アンジュ・レッチアによる没入型映像作品《(D’)après Monet(モネに倣って)》(2020)である。本作は、セシル・ドゥブレ(オランジュリー美術館元館長/現パリ国立ピカソ美術館館長)のキュレーションのもと、モネへのオマージュとして制作され、日本では初公開となる。睡蓮の池を出発点に、モネ自身や彼の家、睡蓮、そして水面に映る光景が、自然の観察と幻想のあいだを行き交いながら重なり合い、鑑賞者の記憶に残るイメージをかたちづくる。

本展を監修するシルヴィー・パトリ(オルセー美術館学芸員)は、「近代化によって世界が大きく変わっていくモネの時代を、私たちの時代と重ね合わせながら、モネが自然をどのように捉え、その表現を更新していったのかを問い直したい」と語る。花咲く庭の一角から都市の駅、荒海、霧、そして睡蓮の水面へ。本展は、自然と向き合う方法を探り続けたモネの創造を、あらためて見つめ直す機会となるだろう。