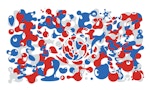モネは生涯を通じて、雪景色から繰り返し着想を得てきた。セクション3では、1869年に描かれた《かささぎ》を中心に、「白」という色をめぐるモネの試みが紹介される。

同作は修復を終えて初めて披露。画面には、桃色や紫を帯びた雪、青みがかった灰色の垣根、黒いかささぎの影などが織り込まれ、たんなる白一色ではない豊かな色彩が表現されている。雪は風景の凹凸を覆い隠してしまいがちだが、モネは浮世絵の雪景にも通じる色面の重なりによって、静かでありながら奥行きのある空間を描き出している。

1870年代に入ると、モネは自然の風景だけでなく、近代都市の情景にも積極的に目を向けるようになる。パリ中心部に位置するサン=ラザール駅の近代的な建築は、モネの強い関心を引き、11〜12点におよぶ連作が制作された。
セクション4で紹介される《サン=ラザール駅》(1877)では、蒸気機関車が吐き出す煙が画面を満たし、自然と人工の境界が曖昧に描かれている。また、《パリ、モントルグイユ街、1878年6月30日の祝日》(1878)では、政治的対立の終結を祝う祝祭の日の賑わいが、当時のパリの街並みとともに生き生きと表現されている。


1878年から81年にかけて、モネはセーヌ川沿いの村ヴェトゥイユに移り住む。ここでモネは、庭の端や川の土手にイーゼルを据え、四季の移り変わりとともに姿を変える自然を丹念に観察し続けた。セクション5では、このヴェトゥイユ時代に制作された作品が紹介される。
アルジャントゥイユとは異なり、ヴェトゥイユは工業化の影響をほとんど受けていない、静かで平凡な村だった。その変化の少なさこそが、光や天候といった要素を際立たせる舞台となった。同じ視点から繰り返し描かれた風景は、1880年代以降に本格化する連作風景画の先駆けであり、後年の《睡蓮》へとつながる重要な試みでもある。《ヴェトゥイユの教会》(1879)や《氷塊》(1880)に見られる、凍結したセーヌ川のきらめく水面は、水辺と睡蓮の世界へと向かうモネの視線を、静かに予告している。