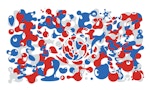1880年代、モネは家族を残してフランス各地を訪れ、ときには国外にも滞在しながら制作を続けた。ひとつの土地に拠点を置きつつも、あえて移動を重ね、地形や季節、光の条件が異なる場所に身を置くことで、自身の絵画表現を試し、広げていった。セクション6では、そうした「探索」の時代としての1880年代が紹介される。
1886年9月から11月にかけて滞在したブルターニュ地方の島ベル=イルでは、荒れ狂う海と、波に打たれる岩が主なモティーフとなった。海を見下ろす大胆な構図は、モネの作品のなかでも、とりわけ浮世絵との共通点を直感的に感じやすい例といえる。

また、オランダを訪れた際に制作された《オランダのチューリップ畑》(1886)では、光の反射や鮮やかな色彩が、土地特有の雰囲気と結びつき、風景体験そのものを強く印象づけている。

モネが自然や風景の捉え方を、日本美術、とくに浮世絵から学んだことはよく知られている。セクション7「ジャポニスム」では、その影響をたんなる好みや異国趣味として扱うのではなく、モネの風景画をかたちづくった「見る方法」の変化として捉え直している。
1890年代に入ると、モネは単独のモティーフを描くことが減り、同じ主題を繰り返し描く「連作」に本格的に取り組むようになる。ポプラ並木や積み藁、大聖堂といった題材を、同じ視点から、時間帯や天候、光の違いによって描き分けることで、風景は特定の「場所」から、移ろい続ける「現象」へと変わっていった。

その代表例が、1892年と翌93年にルーアンに滞在して描かれた大聖堂の連作である。セクション8に展示される《ルーアン大聖堂 扉口 朝の太陽》や《ルーアン大聖堂 扉口とサン=ロマン塔 陽光》(いずれも1893)は、モネが建築物そのものに集中的に向き合った、初めての試みとされている。画面は大聖堂の正面に絞られ、街の様子はほとんど描かれない。その結果、曇り空や晴天、朝や夕方といった光の変化そのものが、絵画の主題として際立っている。