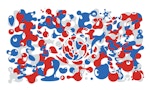パンリアル美術協会から刺激を受け、1959年に誕生したケラ美術協会は、よりラディカルに素材と形式の解体を推し進めた。「細胞」を意味するラテン語「ケラ」に由来するその名が示す通り、運動の拡張性を志向し、日本画の顔料に限らず、油絵具、エナメル、漆、布、石、泥などあらゆる素材を導入した。本展では岩田重義、楠田信吾、久保田壱重郎、榊健、野村久之らの作品が並ぶ。
楠田信吾の《オカサレタ・タブー》(1960)は、画面をえぐるように傷つけ、絵画を物質として露呈させる作品だ。また榊健の《Opus.63-4》(1963)は、白いキャンバス自体を湾曲させ、ミニマルな造形のなかに強い立体性を孕ませている。「より純粋な絵画」を追求した果てに、日本画はもはや絵画という枠組みすら問い直す地点へと至っていたことがわかる。


森は、こうした作家たちが京都市⽴美術⼤学(現・京都市立芸術大学)で正統的な日本画教育を受けていた点を重視する。日本画の歴史と制度を背負ったうえで、それをいかに突破するか──その葛藤こそが、前衛日本画を生んだ原動力だった。
具体美術協会など日本の前衛美術は海外を含め、紹介される機会は増えてきたいっぽうで、前衛日本画に正面から向き合あえるこれほどの機会はほとんどなかった。それゆえか、本展には海外の研究者からも問い合わせが寄せられているという。日本画の世界の内部で格闘し、時代を超克しようとした画家たち。その生き様と可能性は、いまを生きる私たちに日本画という表現の未来を考えるための、確かな問いを投げかけている。