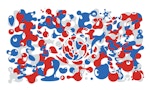7章の主役は、1960年代から80年代生まれのアーティスト。二次元と三次元がどのように融合しているかを、多様な表現からによって紹介しようというものだ。「側の器」と題したシリーズを追求する現代画家・増子博子(1982~)による《移ろう景色 皆川マスの絵付けより》(2020)は、益子の絵付師・皆川マス(1874~1960)の仕事に触発されて制作した作品。陶器の絵付けを作家の視線でとらえなおすプロセスを具現化している。



最終章の「焼成と形象」は、陶芸における焼成について問いかける現代作家の作品を紹介するもの。ここで、とくに注目したいのは、鯉江良二(1938~2020)による大作《土に還る》(1990年代頃)だろう。「土に還る」シリーズは作家が30代の頃に注目された代表作のひとつで、自らの顔で石型をつくり、そこにシェルベン(衛生陶器を粉砕した粒状の材料)を押し固めたオブジェ。時の推移とともに顔面のかたちが崩れ落ち、最終形は原初の状態に帰還していく姿が表されている。やきもののによるで表現可能性の幅広さをも問いかけるようだ。

また、国際的に高い評価を得ている桑田卓郎(1981〜)の作品も、あらためて焼成の観点から見てほしい。《茶垸》(2024)に見られるような大きなひび割れは桑田作品のアイコンだが、こうしたディテールは「火の成り行き(無為)と作り手の創意(作為)の間に生まれる」ものだ。本展では、桑田の原点とも言える益子陶芸展受賞作品《色彩サラウンド》(2006)もあわせて見ることができる。

陶芸作品展は数多く開催されているが、本展は現代陶芸の越境性を絵画との関わりから眼差すものとして意欲的な企画だと言えるだろう。現代陶芸が従来の文脈と異なる場面で露出することが多くなってるいまだからこそ、陶芸が持つ意味を考えたい。
なお、本展では「ジョルジュ・ルオーの手仕事」も同時開催。こちらはルオーの陶磁器への絵付けとともに、平面作品にみる筆触や彩色、画材や制作プロセスに改めて注目したもので、ルオーにおける手の仕事のあり方や工芸性の表れを見ることができる。