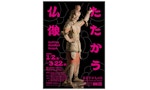岡本、福沢が「メキシコ美術展」以前からメキシコ美術からの影響を受けていたのに対し、芥川、利根山、河原は同展から直接的な刺激を受けたといえるだろう。
海外訪問の経験を経て、日本の伝統文化に根ざした現代美術のあり方を模索していた芥川は、「メキシコ美術展」において展示されていたルフィーノ・タマヨの色彩に強く惹かれる。

その色彩の源泉にメキシコの民芸品があることを見出した芥川は、民衆のための芸術としての壁画運動へも共感し、日本において古代と現代を接続するような作品を制作するようになっていく。会場では当時の日本人の実存とともに、『古事記』を始めとする古代からのアイデンティティを探るような作品を見ることができる。

労働者など戦後の社会状況で生きる人々の営みに寄り添おうとした利根山光人は、ヨーロッパからの美術の無批判な受容に否定的だった当時、利根山は、「メキシコ美術展」に強い刺激を受けた。59年にメキシコに渡り、メキシコの人々の営みにより肉薄し、その精神に共感しながら作品を制作することになる。

やがて利根山はメキシコ国立近代美術館で個展を開催。さらに日本でのダビッド・アルファロ=シケイロスの個展開催にも尽力した。以後、日墨を行き来しつつ、メキシコへの深い愛情をもって遺跡や民芸品を尋ねながら作品に反映させていった、まさにメキシコをその創作の中心に据えた作家といえるだろう。
いっぽう、戦後の現代美術を代表する日本人作家のひとりである河原温は、メキシコ美術に影響を受けながらも、独自の距離感をもって対峙した。河原は「メキシコ美術展」に一定の評価を下しながらも、そこにある浅薄なエキゾチシズムについては批判的だった。

しかし河原は59年に父親の赴任先であるメキシコに渡り、62年まで美術学校の学生として滞在。当時の活動の詳細はわかっていないことが多いが、わずかな資料からは、言語やコミュニケーションにまつわる実験を試み、コンセプチュアルな展開につながる下を準備していたことがわかる。さらに、68年にはメキシコを再訪問。「日付絵画」のシリーズ「Today」においては、メキシコでの経験から移動や多言語の要素が加わるなど、その活動にはメキシコからの影響が存在していたことがうかがえる。