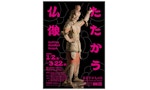第4章「画題の広がり」では、明治10年代後半から晩年までの、明治の激動のなかで国周が描いた作品を紹介。例えば、当時世の中を震撼させた出来事といえる西南戦争であるが、国周はこうした事件も、実録的なリアリズムを取り入れた武者絵ではなく、徹底して役者絵として表現することにこだわった。

また、本章では国周の絵の力に対峙できる肉筆画に注目したい。なかでも《墨堤観花図》(1892、明治25年)は、帝国博物館総長の九鬼隆一の依頼で描かれたもの。花見を楽しむ人々の仕草や装いが仔細に描かれた、華やかな様相を楽しんでほしい。

以降も、国周の役者絵は古くからの歌川派を引き継ぎ続けた。いっぽうで、美人画は柔軟に時代の流行を取り入れ、歳の近い弟子の楊洲周延とも協調する姿勢を見せていた。このように、多彩な国周の姿勢を見ることができるのも本展の特徴となっている。

近年、注目が集まる明治以降の浮世絵の豊かさ。歌川派を未来につなげようとした豊原国周もまた、時代をつくった一人であったことを、改めて知ることができる展覧会だ。