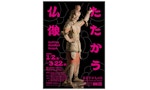書風の変化を楽しむ「古筆切の書風」
能書家といっても、時代、人によってその書風は様々。この時代の古筆は、貴族文化を反映したみやびやかな書風から、武家の台頭や、和歌そのものの受容の変化などで、個性や実用性が重視される書風へと変移していく。「かなの頂点、高野切」「優美な書風と個性的な書風」「実用性を兼ねた書風へ」「筆者名がわかる切」の4つのポイントから、当代を代表する書き手たちの作品にその変化を読み取っていく。読下し文とともに書風の特徴の丁寧な解説もあるので、「読めないし、見どころがわからない」と思っている方も楽しく追えるだろう。

注目はもちろん、本展が収蔵後初公開となる「高野切」だ。現存する最古の『古今和歌集』の書写本であり、かなの最高峰とされているもの。なかでも本作は、巻第十九に4首のみが記載される「旋頭歌(せどうか)」(五七七・五七七の6句からなる和歌の様式のひとつ)の題字を含めた全4句が揃う貴重な断簡になっている。料紙にほどこされた雲母砂子(きらすなご)がよく見える照明になっているので、そのきらめきとともに、漢字混じりのかな2首、かなだけの2首、ふたつの筆を堪能して。

様々な書風からは、自分の好みを探してみよう。古筆切の楽しみは広がっていくはず。また著者が判明しているものからは、書体にいにしえの人の性格や人となりを想像してみるのも一興だ。