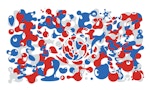美術館という箱を超えることの重要性
──先ほど、復興の名のもとの開発への違和感を口にされていましたが、まさに現在の兵庫県立美術館は被災した兵庫県立近代美術館を引き継ぎながら、湾岸の埋立地につくられた美術館です。安藤忠雄氏の思想を反映した、強い個性を持った建築のこの館で、おふたりがどのようなパフォーマンスや企画をするのかは、とても興味深いです。
森山 震災後の風景として、この巨大な美術館という箱をどのように解釈するか、というのもひとつのテーマだったかもしれません。この箱に注目し、どのような経緯でこの場所に建っているのか、ということを考えるだけで、見え方が違ってくる。
この箱を動力をもたない船、つまり「艀(はしけ)」だと想定して、これに外からどのような動力を与えるか、ということが重要です。誰が、何が動力になって、どこに向かわせるのか。
それは役者やパフォーマーが持つ「依代(よりしろ)」としての役割とも重なってきます。第三者が見たときにこの「依代」がどのように見えるのか。それは100人いたら、おそらく100通りの答えがあるでしょう。その多様な解釈を生み出す役割を、僕という素材が担っているとの考えを元に、梅田さんと制作を進めています。

梅田 役者というのは、自分ではない誰かの人生を生きることができる仕事ですよね。鑑賞者は、役者が演じる誰かに感情移入をしたり、自身の経験を重ねることで、役者の身体を媒介して、自分ではない誰かの人生や自分が経験してこなかった出来事を、当事者であるかのように想像することができる。それは演劇やパフォーマンスという表現形態の特殊性というよりは、美術館で作品を鑑賞するときに得られる、根源的な体験のひとつではないでしょうか。
今回、会場では未來さんや神戸に関連する人々の音声を、例えばダイヤル式の電話機やラジオなどで受信して、観客がアクセスすることができます。美術館の体験として多くの人がイメージする形態とは少し異なりますが、むしろ美術館が本来持ち得る機能を体現する手段として提示しています。

森山 いま、梅田さんは役者の話をしましたけど、僕にとっては踊りにおいても同じことが言えると思っています。主体的に自分の踊りたいものを踊るのではなく、僕にとって踊りとは他者との関係値によって立ち上がってくる身体であり、アクションであり、表現なんです。
僕が現在、運営にも関わっている「Artist in Residence KOBE」も同様で、こういったプロジェクトの運営も他者との関係なくしては立ち上がらない表現です。役者も踊りもプロジェクトの運営も、僕にとっては同様に身体的な表現だと言えます。そしていずれの表現にせよ、媒介者であることが僕にとって重要なことなんです。

──災害という事象に対してアートが直接的になにかできるわけでは当然ないのですが、いっぽうで災害について思考する領域を広げ、多様な関係性を構築する場としての役割が、アートの機能だと言えるのかもしれませんね。
梅田 今年の初め、能登半島地震が起きた直後に、何人かの友人から僕のところに連絡が来ました。「なにか自分にできることはないか」と。僕は去年、能登半島の珠洲市で展覧会に参加していたので、いまでも何らかのつながりがあると思ったのでしょう。大きな災害が起こったときに、その土地との関わりがなくとも、身近なところから何かしらの接点を持ちたい人は相当数いると思います。そういった人たちの中継点になれるような場づくりに、作品制作を通して関わっていけたらいいなと思います。