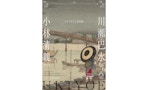東京・丸の内の静嘉堂文庫美術館で「超・日本刀入門 revive― 鎌倉時代の名刀に学ぶ」がスタートした。会期は8月25日まで。担当学芸員は山田正樹(静嘉堂文庫美術館 学芸員)。
本展は、同館が丸の内に移転する前の世田谷区岡本で開催された「超・日本刀入門」のリバイバルとなるものだ。昨今の刀剣ブームから刀剣の鑑賞機会が増えている現在において、刀剣を初めてみる人、またはあらためて学びたい人に向けた入門編の内容となっている。
会場では、「日本刀の黄金時代」とも言われる鎌倉時代の名刀を中心に、国宝・重要文化財を含む23振りが4つの展示室にわたって紹介されている。1章では、直刀・太刀・刀(打刀)・脇指(脇差)・短刀・剣・薙刀・槍と、時代やその要請によって変遷してきた日本刀の分類から、太刀・刀・脇指・短刀・槍をピックアップし紹介している。比較しながら鑑賞することで、刀がその時代の戦闘スタイルや、使う者の身につけ方によって変化してきたことがうかがえるだろう。また、そういった時代の要請にあわせ太刀から短くつくり直された「大磨上げ」のすがたも見ることができる。


2章では、刀剣の時代別・産地別に見られる違いに焦点を当てる。平安時代から江戸時代末期までの刀剣は、制作時期の観点から慶長初年(1596)をさかいに「古刀」と「新刀」の大きくふたつに分けられる。また、「古刀」には5つの主要生産国、山城(京都)・大和(奈良)・相模(相州、神奈川)・備前(岡山)・美濃(岐阜)が存在している。本章では、美濃を除く4つの国の鍛刀法に注目するとともに、各地の鍛刀法を取り入れながら独自の発展を遂げた九州・筑前の作風についても紹介されている。



同館のなかでも1番広い展示室となる3章では、館蔵の重要文化財である8振りの名刀と、鎌倉時代の慶派仏師によるものとされる仏教影刻の名品、重要文化財「木造十二神将立像」の7軀もあわせて特別公開されている。



最終章となる4章では、名刀の見どころに加え、その名刀を所持していた武将との逸話についても目を向けている。こういったその刀剣ならではの逸話は、昨今の刀剣ブームの理由のひとつでもある。ここでは、本多忠為の《一文字守利》、直江兼続の《後家兼光》、向井忠勝の《古青江守利》が紹介されている。

また、館内ホワイエには、足利時代からの金工の名家である後藤家による刀装具も紹介されているためお見逃しなく。本展で基本的な刀剣の見どころから鑑賞方法、エピソードまでと様々な楽しみ方を知ることで、今後の刀剣との出会いがより豊かなものとなるだろう。