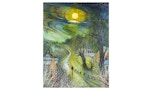東京駅から徒歩圏内の一等地に、待望の新美術館が開館を迎えた。1月18日開館のアーティゾン美術館は、1952年に開館したブリヂストン美術館を前身とする新たな美術館。昨年竣工した高層ビル「ミュージアムタワー京橋」の1~6階に位置し、延べ床面積は6715平米、展示室の総面積は2100平米を誇る。

アーティゾン美術館でまず気をつけたいのが、チケットの購入方法だ。同館では、チケットの日時指定予約制を導入。これによって混雑緩和による快適な鑑賞環境を提供するとしている。ウェブ予約チケットが完売していない場合のみ当日券もあるが、あらかじめ購入して美術館へ向かいたい。

館内の1~2階は吹き抜けとなっており、高さ8メートルもの高透過大型ガラスによって明るい空間が広がる。



展示室への入口には、日本の美術館では珍しい高性能の危険物検知ボディスキャナーを採用。このスキャナーを通過し、いよいよ展示室へと向かう。展示室は4~6階にあり、順路は6階→5階→4階という「下り」となっている。

開館記念展は「見えてくる光景 コレクションの現在地」
展示室は、ひとつの展示室としてはもっとも巨大な6階、階下を見下ろせる吹抜部分がある5階、そして石橋財団コレクションを中心に展示する3つの小部屋が特徴的な4階で構成。今回、この3フロアすべてを使用するのが、開館記念展「見えてくる光景 コレクションの現在地」(〜3月31日)だ。

本展では、アーティゾン美術館を運営する石橋財団のコレクション約2800点のうち206点を一堂に展示。同展は第1部「アートをひろげる」と第2部「アートをさぐる」から構成されている。
第1部に並ぶのは、1870年代から2000年代までの約140年間の東西の名品。これらを「ひとつの地平」として並べることで、時間、空間を超えた美術の風景を一望するという試みだ。

1部の出品作家は、エドゥアール・マネから、アンリ・ファンタン=ラトゥール、ポール・セザンヌ、ピエール = オーギュスト・ルノワール、ヴァシリー・カンディンスキー、 青木繁、マーク・ロスコ、ジャクソン・ポロック、草間彌生、そしてピエール・スーラージュまで多岐にわたる。

教育普及部長の貝塚健はこの展示について、「約140年間の近現代美術を6階で見ていただく。壁の切れ目から次の空間の気配を感じ、曲がるごとに違う景色を見てもらいたい」と語る。
とくに注目したいのは、新収蔵品だ。アーティゾン美術館は休館中も作品の収集を行っており、そのうち31点がここで紹介されている。例えば、コンスタンティン・ブランクーシ《ポガニー嬢Ⅱ》(1925、2006鋳造)、ヴァシリー・カンディンスキー《自らが輝く》(1924)、マーク・ロスコ《無題》(1969)、草間彌生《無限の網(無題)》(1962頃)などだ。

こうした2010年代の新収蔵について、貝塚は本展カタログのなかで「従来の骨格を維持し生かしながら、その全体像を大きく広げるものだった」と語っている。
7つのテーマでコレクションを紹介
続く第2部は、5階と4階で展開されている。2部は、収蔵品を「装飾」「古典」「原始」「異界」「聖俗」「記録」「幸福」という7つの普遍的なテーマに分け、美術を掘り下げようというもの。

例えば「装飾」では、人間の根源的な欲求としての装飾を示すため、石橋財団コレクションでももっとも古い年代の作品というイランの《幾何文台付鉢》(紀元前4000)から、エミール・ガレ、藤島武二、アンリ・マティスといった作家たちによる作品を展示。立体や平面に見られる装飾への普遍的な情熱を提示する。

また「聖俗」では、エジプトのハヤブサ神像からギリシャのヴィーナス、ジョルジュ・ルオーの《郊外のキリスト》(1920-24)、そして《洛中洛外図屏風》(17世紀)までを紹介。人間の、聖なるものを眼前に定着させたいという願望と、それとは対称的な俗なるものにも惹きつけられる性質を古今東西の美術によって見せる。



新たな地平、切り拓けるか
1952年のブリヂストン美術館開館からおよそ70年。アーティゾン美術館館長の石橋寛は「ブリヂストン美術館の伝統を受け継ぎながら、新しい時代に向けて大きな一歩を踏み出す」と意気込む。
「創造の体感」をコンセプトに掲げる同館。4月からは新たな試みである現代美術の展覧会(「鴻池朋子 ちゅうがえり」「Cosmo-Eggs」)もスタートする。「アート(芸術)」と「ホライゾン(地平)」を組み合わせ、美術の新しい地平を目指すアーティゾン美術館の今後に期待したい。