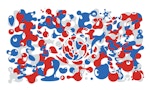長谷川新 月評第3回 「額装の日本画」展 光背(オリオール)試論
村上春樹が新作『騎士団長殺し』において主人公に説明させているように、「日本画」とは明治以降に仮構されたジャンルであり、そのこと自体は指摘されて久しい。「額装の日本画」展は、全国の美術館が厳しい予算内で試行錯誤しているであろうコレクション展の技術開発としても素晴らしく、本展をたんなる制度依存や無根拠性の暴露、そこからの再始動宣言というような、幾度となく繰り返された身振りに回収してはならないように思われる。

もちろん、本展も全体としては、そういった既存の言説をたどり直すものであったことは否めない。また、額装の日本画という形式自体が持つ表象の問題についても踏みこんだ議論が必要だと感じた。例えば鼓常良(つづみつねよし)が日本の芸術を総括する際に用いる「無框性(むきょうせい)/無限界性」と、「額装の日本画」は明らかに折り合いが悪く( 小田部胤久(おたべたねひさ)の指摘を待つまでもなく、ここにはゲオルグ・ジンメルの額縁論の影響がある)、「額縁があつても無限界性の作用は行はれなければならぬ」(『日本藝術様式の研究』、1933年)という「難題」に、同時代の人々がどのように向き合ってきたのかについての興味は尽きない。しかし、神宮紙や岡大紙といった大型和紙の開発による作品の巨大化や、団体展・公募展での出品規定の変遷及び額装の義務化、さらには表装替えという保存技術と並置されるなかで見えてくる日本画の厚みの提示自体は、非常に説得的である。とりわけ、いわゆる「会場芸術」をめぐる議論については、「床の間芸術」と揶揄される作品群の大きさや形態への筆者の認識を、修正する必要に迫られた。

このような意義深い展覧会だったからこそ、ここでひとつの試論を展開したいと思う。ジョルジョ・アガンベンは『到来する共同体』のなかで、聖人の身体から発せられる「光背(オリオール)」について、トマス・アクィナスを参照しながら次のように論じている。聖人たちは「完成状態」にあるのであり、「本質的なものは何ひとつそれらに付加されえない。しかしまた、なおそのうえに付与されうるものがある」。この矛盾した「非本質的な付加物」が光背である。「終点にまで到達してしまった存在、そのあらゆる可能性を使いきってしまった存在は、こうしてひとつの付加的な可能性を贈与として受けとる」。
ここでアガンベンの議論は旋回する。到来する世界はいっさいの破壊の後にまったく新しい世界を開始するのではなく、「ちっぽけな位置移動」によっていまの世界とわずかに違っているにすぎない。「すべての物をほんの少し脇へずらすだけで十分だ」。この「位置移動」は、すでに完全な世界を複数化するという困難において「光背」と一致する。完成した後になってなおも/ようやく到来するひとつの可能態、「なんであれかまわないもの」。移動性を付与することでアウラ(物質と空間の一致)の喪失に加担する「額縁(オリオール)」を、そして、完成した世界でのあらゆる表現行為の否定において出現した「インスタレーション(ちっぽけな位置移動)」を、制度論ではなく存在論的に、私たちはとらえ直すことができないだろうか。
(『美術手帖』2017年6月号「REVIEWS 10」より)