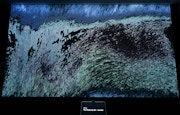「坂本さんは音楽の『聴いてもらい方』をずっと考えていた」
──皆さんは、長らく坂本さんの作品や展覧会の制作などでお付き合いされてきたと思いますが、それぞれの坂本さんとの出会いやその印象をお聞かせください。
畠中実(以下、畠中) 直接私が担当した企画としては、2005年に「PLAYING THE PIANO/05」のツアーのために来日していた坂本さんと、同時期にICCで開催中だった「ローリー・アンダーソン 時間の記録」の関連イヴェントとして、そのツアーメンバーでのコンサートが最初ですね。その頃はまだ実際のところ僕なんかが近寄りがたいぐらいでしたが(笑)。


コンサート『The Record of the Record of the Time』
写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
高谷史郎(以下、高谷) 僕は1990年頃に初めて出会って、最初にお仕事をしたのは1999年の「LIFE a ryuichi sakamoto opera 1999」です。それまでもコンサートを見に行かせてもらったり、ニューヨークのスタジオに遊びに行ったりしていました。プライベートでお会いした時は、僕らが音楽関係者じゃないからか(?)ラフな雰囲気で気楽に接してくれていると感じていましたが、コンサートの楽屋などでお会いするときは独特のオーラと緊張感がありました。

畠中 その後、2010年代になって東日本大震災の後くらいから、坂本さんの世界に対する認識の変化によるものだと思いますが、音楽のつくり方やアプローチも変わったと思います。『async』(2017)が象徴的ですね。それまではポップスターとしての「坂本龍一」でもあったのですが、そこからどんどん素の坂本さんになっていく感じがありました。ご病気のこともあったと思いますが、その変化のなかで、高谷さんというベストパートナーとともに、インスタレーション作品を次々と発表されていく。「Ryuichi Sakamoto | async 坂本龍一|設置音楽展」(ワタリウム美術館、2017)と「坂本龍一 with 高谷史郎| 設置音楽2 IS YOUR TIME」(ICC、2017)は、設置音楽というコンセプトを突き詰めていったものだと思います。
高谷 そういう意味では、僕のなかでは、坂本さんは音楽の「聴いてもらい方」をずっと考えてられたのかなという気はしますね。1980年代から90年代には、ポップミュージックとして多くの人に広く聴いてもらえるように、レコードやCDの流通システムのなかで、それを実験していた。それはそれですごく重要な方法だと理解されていたと思うんですが、同時に僕がやりたいのはこんな音楽なんだけどこれを聴いてもらうためには、どういう環境が最適なんだろうと、探っていらっしゃったと思います。

撮影=丸尾隆一
写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
──とくに坂本さんの音楽は聴取環境によって大きく聴こえ方が変わりますよね。
高谷 そうですね。坂本さんにとってインスタレーションというかたちが、最終形態かどうかわからないですが、すべては、お客さんにどう音楽を届けるか、という実験だったのかなと思います。劇場をつかったオペラもあるし、マルチトラックで⽴体的な⾳響空間をつくることができれば、お客さんの立ち位置によって全然違って聴こえる。今回真鍋さんがやっている《Generative MV》(2023)なども、お客さんが作品にコミットできるというシステムも、その実験のひとつとして考えられますよね。

真鍋大度+ライゾマティクス+カイル・マクドナルド《Generative MV》(2023)
撮影=冨田了平
写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

坂本龍一の「データ」を継ぐ
真鍋大度(以下、真鍋) 僕は2014年の札幌国際芸術祭のときに《センシング・ストリームズ―不可視、不可聴》(2014)をつくったときに、はじめて長く一緒に仕事をしました。このときは坂本さんが最初のガンになられたタイミングで、ご本人とのコミュニケーションはLINEやメールでが多かったです。コロナで実現できなかったものもありましたが、本当にいろんなアイデアを持っている方でしたね。僕たちは坂本さんの演奏データや映像データなどをたくさん録りましたが、坂本さん本人は自分やその演奏を素材として提供したら、あとは好きに使って、というスタンスでした。アウトプットは任せたと。亡くなってしまって、見ていただけなかったものもたくさんあります。





畠中 1997年に岩井俊雄さんと行ったコンサート「MPI X IPM」でも、自分はあくまで演奏者として、素材に徹するという考えがどこかにあった。テクノロジーに対して、自分が使えるものとそうじゃないものがはっきりわかっていて。自分がやらなくてもいい部分はプロフェッショナルに委ねてきた、それは一貫してますね。
高谷 もうそれはその人自身の作品として、今回の場合は真鍋さんの作品としてまとめていけばいい、という考えだったんじゃないかと思います。でも、記録が残っているってすごいことで、坂本さんも、ポール・ボウルズのレコーディング音声や(ウィリアム・バトラー・)イェイツが詩の朗読をしている録音を自身の作品に取り込んだりされていますが、坂本さん自身の演奏データがMIDIのような情報で残っていることはすごいことで、作品化できるかは別の話にしても 次の世代の人が思いもよらない方法で使うのかもしれないので、どんどんアーカイヴしていくことに意味があると思います。
真鍋 純粋に演奏をデータとして残すこともそうですが、それを何か面白いことに使うことの方に坂本さんの興味もあったと思います。AIにも興味を持たれていましたし、データを取っておけばどこかで活用され、違う作品が生まれることに意識的だったのかなと。「これだけデータをとっておけば、後はAIがやってくれるかな」と冗談っぽくおっしゃられていましたが、高谷さんが言ったようにそのデータを取っておけば後で何かいろいろな活用が生まれる。
高谷 とくにMIDIデータなんかは、もっと先の未来で何かになる可能性があるわけだから。

写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
畠中 アルバム『BTTB』(1998)の初回盤にも、MIDIデータのフロッピーディスクと譜面がついていて、今回真鍋さんはそれをネットオークションで買ったんだよね(笑)。でも、そもそもなんで音楽をMIDIデータで販売していたのか、そこが重要ですよね。ただ音楽を聴くメディアということだけで言えばCDでいいのだけど、演奏データもつけて販売する。初回盤を買ってくれた人がMIDIピアノをもっていれば、本当にそのピアノで聴いてもらうということも考えていたということだし、もちろん本来音楽は楽譜で流通していたものだけれど、たんなる複製音楽ではない流通の仕方を考えていたのでしょうね。
高谷 今回の毛利悠子さんの作品《そよぎ またはエコー》(部分を「坂本龍一トリビュート展」のために再構成、2017/2023)も、MIDIピアノが自動演奏しているのだけど、その鍵盤のタッチにドキッとする。

手前が毛利悠子《そよぎ またはエコー》(部分を「坂本龍一トリビュート展」のために再構成、2017/2023)
撮影=冨田了平
写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
畠中 現場で鍵盤が動いているだけで、姿が見えなくても坂本さんの痕跡が見えますよね。
真鍋 坂本さんの演奏をデータ化するために、撮影していたときですが、スタジオにはグリーンバックとカメラを設置した場所があって、その後ろに僕らがオペレーションしているスペース、そして少し離れたところにサーバールームがあって、実際にデータ処理してるのはサーバールームなんですけど、坂本さんはそこまで来て、そこで何が起きているのか、エンジニアに質問していました。そういう意味でテクノロジーに本当に興味があるんだなと思いましたね。
高谷 そのテクノロジーが、使えるか使えないか、わかるところまではわかっておきたいという判断だと思います。よく「実験」という言葉を使っていましたが、最終的に作品として発表するときには、一定のクオリティに達していないと、途中でもはっきりと今回は無理と判断されていましたね。ここまでやったけど、実験的なものとして中途半端な状態で発表するのではなく、寝かしておこうと。

──作品として発表するクオリティと実験としての面白さは、別の基準として考えられていたと。
高谷 そう思います。同時に、坂本さんが実験的な楽器を演奏しても、坂本さんの音楽になる面白さもありました。例えば坂本さんのプリペアド・ピアノの演奏はすごいです。単純な言い方ですが、普通プリペアド・ピアノを演奏するとどうしても、いかにも「実験音楽」のように聴こえてしまうのですが、坂本さんが弾くと坂本さんの楽曲になっている。
畠中 プリペアド・ピアノは、ピアノを異化するということだと思いますが、誰が演奏しても音色が似てしまうという傾向もあり、たしかに音楽家としての記名性を残していくことには難しさがあるかも知れません。
高谷 坂本さんは津波で被災したピアノも弾かれていますが、実際に使いこなそうとしているし、使いこなせたと思います。調律が狂っていたり音が出なかったりする鍵盤を叩きながら、音楽になるポイントを探していくという感じでした。また、京都市立芸術大学で(ベルナール&フランソワ・)バシェの音響彫刻の録音をされた時も、坂本さんの「音の出し方」は他の方の「演奏」とは音が全然違いました。音響彫刻に触りながら、どのような音が出るのかをひとつひとつ確かめながら、これは使えるという音を見つけ出しては録音してリアルタイムに編集するような合理性もありました。

真鍋 僕がまだ学生の頃にalva noto(カールステン・ニコライ)と坂本さんが発表された『Vrioon』(2002)というアルバムに衝撃を受けました。自分も当時は電子音楽をかじっていたのですが、ノイズとピアノで、こんなに綺麗な音楽ができるのかと。当時は実験的なものがほとんどだったなかで、突然美しいものがでてきたという感じでしたね。
高谷 当時はみんな実験的にラップトップ(パソコン)から、いかにノイズを出せるかをやっていましたよね。再生中に急にUSBを抜くとか(笑)。それはそれでとても面白かったけど。そんななか、そのノイズをも取り込んで、とても美しくまとまったカールステンと坂本さんの音楽が発表された。
畠中 そうですね、当時はそれこそ「デジタル時代のノイズ・ミュージック」をみんなつくっていたんだけど、それがどんどんエステティックに変わっていった。それはこのalva notoと坂本さんの共作の影響が大きいと思います。坂本さんなりの音楽のエステティックのなかに、ノイズやグリッチが入ってくるんだけど、そうするとそのグリッチも坂本さんの音楽になっていた。

真鍋 やはり自分もやっていた電子音楽やノイズミュージックで、坂本さんがやると全然違う仕上がりになっていたのは衝撃でしたね。同時に、僕にとっての坂本さんは、やはりつねに実験的なことをやろうとしていた人ですね。そしてできあがった作品でも、新たに発表するときには、必ず新しいアイデアを入れようとしていた。また、世間にそんなに知られていないアーティストとも積極的にコラボレーションされていましたね。僕もそれなりにオーディオ・ヴィジュアルやメディア・アートの分野のアーティストは知っているほうだと思うのですが、坂本さんに「こんな人見つけたけどどうなの?」と聞かれることも多くありました。
高谷 坂本さんは、いまも昔のアーティストにも詳しくて、ちゃんと整理して理解されている。映画や映像、美術のこともすごく詳しかったです。だから、自分でも映画や映像を作ったらいいのにと思ったんですけど「僕は映像はわからないんだよ」っておっしゃっていました。でも僕は、坂本さんの音楽ってものすごく映像的だと、ずっと思ってるんです。だから「Ambient Kyoto 2023」で展示した《async – immersion 2023》も、音と映像が同期していないので徐々にずれていくのですが、それでも映像と音楽があっているように感じられるのは坂本さんの音楽だからだと思います。
畠中 もちろん坂本さん自身の表現もすごいですが、アンテナもすごい。同時にコラボレーションしている相手を尊重しながらも、坂本さんの意向が感じられるものにしていく。例えば真鍋さんとの共作の《センシング・ストリームズ―不可視、不可聴》と高谷さんとのコラボレーション作品は、それぞれ性質の違うものですが、やはり、坂本さん的なものが入っている。同時に真鍋さんと高谷さんの個性もしっかりと感じられる。音楽での共作も、そういううまい押し引きがあったように思います。
真鍋 そうですね。コラボレーションしながら同時に自分が学ぶことをされていましたね。

坂本龍一+真鍋大度《センシング・ストリームズ 2023-不可視,不可聴》(ICC ヴァージョン)(2023)
撮影=冨田了平
写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

坂本龍一+真鍋大度《センシング・ストリームズ 2023-不可視,不可聴》(ICC ヴァージョン)(2023)
撮影=冨田了平
写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
「2023年の内にやらないといけない」
──今回の展覧会開催のいきさつをお教えいただけますか?
畠中 坂本さんが亡くなった直後に、DOMMUNEで真鍋さんと話す機会がありました。そもそもステラークさんがゲストの回だったのですが、御本人と宇川(直宏)さんに了承を得て、番組内で2人で坂本さんへのお悔やみの言葉を述べました。僕らはメディア・アートにとって坂本さんの存在は大きいものとしてとらえていたので、その後もなにかできないかなと連絡取り合いながら、二人で展覧会の企画書を書きました。同時にトリビュート展という性格上、なるべく早く開催する必要があると思いました。時間もなかったので、新作を誰かにつくってもらうとかはあまり考えておらず、資料ベースの展覧会にしようかなと。でも結果的には真鍋さんがいろいろなアーティストにお声がけしてくれて、坂本さんと関わりの深いアーティストの展示だけでなく、坂本さんの残されたデータを素材とした新作のインスタレーションも展示できましたね。

ストレンジループ・スタジオ(デイヴィッド・ウェクスラー,イアン・サイモン)《レゾナント・エコーズ》(2023)
撮影=冨田了平
写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

フォーオーフォー・ドットゼロ(クリスティーナ・カールプリシェヴァ,アレクサンドル・レツィウス)《The Sheltering Sky - remodel》(2023)
撮影=冨田了平
写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
真鍋 自分が関わったもの以外にも、坂本さんに関するたくさん映像や録音データがあるのも知っていましたし、こういう機会がないとなかなか外に出ないだろうなとも思っていました。とくに「Perspective」を演奏されているグリーンバックの映像データなどは、カメラのレンズデータ、ズームデータ、位置データも保存していて、そのまま眠らせておくのは勿体ないなというのがありました。そこで、坂本さんを尊敬する、または坂本さんが尊敬する様々なアーティストに、MIDIデータとカメラデータと撮影した映像を使って新作をつくってほしいと声をかけました。
高谷 ものすごい数のアーティストや研究者とつながりがあるから、誰に声をかけるかなど、考え出したらきりがないですよね。
畠中 そうですね。だから交友関係から考えると、なんでこの人がいないの? と思われることもあるかもしれません。深掘りしようとすれば何年もかけてやるべきですね。今回のトリビュート展は、2023年の内にやらないといけないと思っていたので、ひとまず、という感じですね。

左から李禹煥《祈り》 (2022)、《遥かなるサウンド》 (2022)
撮影=冨田了平
写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
高谷 またやればいいんですよね。トリビュート展2を。坂本さん自身も草月ホールでグレン・グールドのトリビュート・コンサート「グレン・グールド・ギャザリング」(2017)をされていますしね。次につながっていけばいいかなと。
真鍋 じつはまだ声をかけているアーティストもいるので、どこかで追加で作品の発表があるかもしれないです。予算上、そんなことが可能かわかりませんが(笑)。
畠中 そうですね(笑)。今回は坂本さんの音楽・アート・メディア関連という年表をつくりました。そうすると意外と「その他のメディア」の項目が充実していて、とくにインターネット元年(1995)あたりの項目が多くなりました。例えばCM出演なども、コンピュータや携帯電話のものが多くて、当時坂本さんがテクノロジーを使う人のアイコンみたいになっていたことが、よくわかります。同時に本人がインターネットや環境問題など、時代ごとに何に関心を向けていたのかもよくわかる。

──坂本さんは時代によって様々な時事問題や文化事象にコミットされているので、坂本さんを通じて美術や音楽、そして歴史や社会問題を知るという存在でしたね。
畠中 僕の年代は1980年代に坂本さんのラジオ「サウンドストリート」を聴いて、いろいろなものに興味を持った世代なんですよね。坂本さんのラジオを聞いていなかったら、こういう仕事していないかもしれないというくらいです。ブライアン・イーノもマイナーな現代詩も、坂本さんのラジオを通じて知った。そういう意味では坂本さん自身がメディアだったといえますね。
1980年代、時代はニューアカデミズムとポストモダンですから、文化横断的にいろんなものや人が縦横無尽に接続されていきました。坂本さんはそういう時代のなかで、自分が素材になり、他者を素材にして音楽をつくったりと、相互作用のなかで活動されてきた。でも同時に、坂本さんが、新宿高校で学生運動をやっていたことも、1980年代に高度資本主義のなかでその波に乗りながら活動されたことも、2000年代以降の活動家的な側面もすべてつながっていると思うんですよね。
高谷 そうですね。つながっていますね。
昔、武満(徹)さんが邦楽器を使っていることに対して、まだ学生だった坂本さんが批判のビラを撒いたという有名な話がありますが、坂本さんが『TIME』で笙を非常に象徴的に用いられていることは、回り回ってつながっていることだと思います。(何より坂本さんは「時間」をテーマにした『TIME』には笙の音がぴったりだと考えておられたと思いますが、)それは、こんな小さな地球の中で、国とかそういうことにこだわるのはもう終わらせましょう、ということなのかなと。それよりも晩年は、人間はどこから来てどこにいくのかというようなことに興味があったと思います。音楽としてもコスモポリタンであるべきだと。
畠中 この年表も途中経過であって、より解像度を上げて継続的につくりつづけてもいいかなと思います。また、今回はトリビュート展ですが、坂本さんの作家史を俯瞰するような展覧会も必要に思いますね。

撮影=冨田了平
写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]