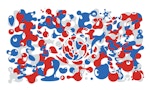中島点子(以下、点子)は、東京を拠点に活動するキュレーターであり、“ノマディック”なギャラリープロジェクト「galerie tenko presents」の主宰者でもある。写真家・現代美術家として国際的に知られる母・花代のもとに生まれ、東京とベルリンで育ち、ロンドンのセントラル・セント・マーチンズでキュレーションを学んだ点子は、帰国後の東京で、空き家やカラオケルーム、自宅のエレベーターといったユニークな空間を舞台に展覧会を企画してきた。
ジャンルや世代を横断し、国際的なネットワークを活かしながら“遊撃的”に展開される「galerie tenko presents」は、従来のギャラリーの枠にとらわれない、軽やかで即興的な運営スタイルによって注目を集めている。
今回のインタビューは、初の“準常設スペース”となる恵比寿の会場にて、イギリス人アーティスト、マーリン・カーペンターの個展「Vintage」開幕から間もない5月下旬に行われた。これまでノマディックに活動してきた点子が、今後どのような展開を見据えているのか──その思考と実践の軌跡をたどる。

遊び場としてのギャラリー
──まず、galerie tenko presentsを始めた経緯を教えてください。
始まりはとても自然なものでした。ロンドンのセントラル・セント・マーチンズでキュレーションを学んだ後、コロナ禍を機に日本に戻ってきた私は、日常の中に「若いアート」のカルチャーがもっと必要だと感じました。当時の東京にはそうした場所が少なく、展覧会のオープニングも保守的で早い時間に終わってしまう。ニューヨークやロンドンのように、アートやファッション関係者、学生たちが集まり交流できる空間を、自分でもつくりたいと思ったのが出発点です。
ちょうどその頃、ニューヨークから来日していたアーティストのマリーシャ・パルゼルと一緒に、都心の空き倉庫で展覧会を開催しました。Instagramやメールで呼びかけたところ、アートやファッション業界の人々が多く訪れ、「東京でもこういうことができる」と実感しました。

次は、自宅で山本靈樹との展示を行いました。彼女は当時16歳で絵を描き始めたばかりでしたが、作品の完成度が非常に高く、実際に展示したところ、半分以上が売れたのです。当初は販売目的ではなく、コミュニティづくりとして始めたプロジェクトだったので、大きな驚きとともに可能性を感じました。
私はベルリンで育ち、2000〜2010年代のアーティスト・ラン・スペースや自主企画展の文化に影響を受けてきました。その精神を自分の活動にも引き継ぎたいと思っていましたが、それで収益が出るとは考えていませんでした。だからこそ、「もう少し続けてみよう」と思い、現在まで活動を続けています。
「galerie tenko presents」という名前も、当初は名乗るつもりはなく、「tenko presents Marysia」「tenko presents Raiki」と展示ごとに呼んでいたものが、自然と定着していっただけなんです。
──当初はどのようなビジョンを思い描いていたのでしょうか?
私のビジョンには、ベルリンでの経験が大きく影響しています。当時のベルリンは家賃も安く、アーティストたちはアパートや空き家で自主的に展示を行い、自ら出会いの場をつくっていました。そうした自由でラフな空気のなかから、多くの才能が育まれていた。その雰囲気に共感し、自分のプロジェクトでも、アーティストや周囲とのコミュニティを大切にし、「一緒に楽しめる場」を育てていきたいと考えています。

──ベルリンと東京で育ち、ロンドンで学んだご経験は、ギャラリーのアイデンティティにどう関係していると思いますか?
最初から明確なアイデンティティがあったわけではありません。活動を重ねるなかで、少しずつ「性格」のようなものがかたちづくられていった感覚があります。私はいつも直感的に、「このアーティストと何かをやりたい」と思える人と関わってきました。自分の作品をうまく言葉にできなくても、強い表現力を持つ人に惹かれる傾向があります。
また、どこかに繊細さや疎外感を抱える人に共感する部分も大きいです。日本で育つなかで、自分自身が「外側にいる」と感じていた経験や、家族や日々の暮らしを大切にしてきた母の価値観が、そうした感覚の背景にあるのだと思います。だからこそ、そうしたアーティストを支えることが、自分のプログラムの中心にあるのです。