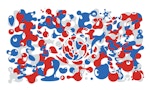変化を起こす場所としての東京
──アートワールドそのものを変えたいという意識もありますか?
はい、あります。ただ批判するだけでなく、「どうすれば変えられるか」を模索したいし、ほかのキュレーターや関係者と対話を重ねながら変化を生み出していきたいと考えています。だからこそ、私はいまも日本にいます。私はこの国が好きだし、日本で何かを変えたい。その思いが、プロジェクトの原動力になっています。
──東京のギャラリー・エコロジー、とくにアーティスト・ラン・スペースやオルタナティブ・スペースについては、どう感じていますか?
私がいまのような自由な活動を続けられているのは、東京という場所だからこそだと思います。ニューヨークやベルリンにはすでに数多くの若くてクールなスペースがあり、私のようなプロジェクトはそのなかに埋もれてしまう。でも東京には、アーティスト・ランやオルタナティブなスペースがまだ限られていて、だからこそ自分の“遊び場”のような感覚で、のびのびと活動できています。

4649や18 Murata、Misako & Rosenとはお互いの活動を尊重し合いながら協力できていて、プログラムの棲み分けも自然にできている。KAYOKOYUKIのように応援してくれる存在もいて、最近は「もっとインターナショナルなことを仕掛けていこう」という空気も感じます。東京のアートコミュニティは、いまとてもポジティブな方向に向かっていると感じます。
もちろん、世代による分断は多少あるかもしれません。東京は広く、すべてのギャラリーの動きを追うのは簡単ではありません。でも、どのギャラリーも収益だけを目的にせず、情熱や責任感を持って活動している。まるで“趣味”のように、それでも「自分がやらなきゃ誰がやるのか」という気持ちで続けている。自然と助け合う関係が生まれていて、それが東京のシーンの強さであり、魅力なのだと思います。
──galerie tenko presentsの展覧会プログラムは、遊び心がありながらも誠実で、流行やマーケットとは距離がある印象です。それはなぜでしょう? また、アーティストはどのように選んでいますか?
多くの場合、ロンドンの学生時代や、アーティストである母のつながりを通じて知り合った人たちと展示をしています。アートの世界はとても小さく、一度その輪に入ると自然とつながりが広がっていきます。イベントや展示の場で仲良くなって、「一緒にやろうか」というかたちで企画が生まれることが多いです。
私にとって展覧会は、たんに作品を並べる場ではなく、しっかりとキュレーションされた空間であるべきです。「tenko presents」という名前である以上、私自身の思想や美学が反映されていることが大事ですし、アーティストにも「何点売れるか」ではなく、「どうすれば面白くなるか」という視点で展示を考えてほしいと思っています。

例えば、自宅のエレベーターで展示をしたときも、その空間の文脈や意味を考えて構成を決めました。そうした空間性やコンセプトを重視するアーティストとの協働が多いですし、私は真剣さのなかに少しユーモアやアイロニーがある展示が好きなんです。
アートはもっと自由であっていい。美しいものだけでなく、“チープ”だったり“汚れている”ように見えるものにも惹かれます。展示が堅苦しさから解放されるような余白や軽やかさを持っていることが、自分らしさなのかもしれません。
もちろん、「面白くしよう」と無理に思っているわけではありません。ただ、自分自身を笑えること、そしてユーモアの力を信じているだけ。いまのスタイルを無理に変えるつもりはなく、自分が信じるやり方をこれからも続けていきたいと思っています。