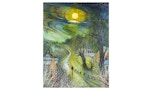第8章「動物狂騒曲」は、幕末に海外から持ち込まれ人々の注目の的となったヒョウと、明治初めに流行したウサギ、ふたつの動物を画題とした錦絵にスポットを当てる。ここでは、見世物となっているヒョウを描いた河鍋暁斎画《今昔未見 生物猛虎之真図》(1860)や、俗謡に合わせて滑稽に踊る「かっぽれ」をするウサギを描いた東柴画《かつぽれかへうた》などを見ることができる。


最後となる第9章「開化絵とその周辺」は、明治維新により急速に変貌していく東京の町や風俗を画題とした「開化絵」を紹介。文明開化後、西洋の文化を取り入れて急速に姿を変える東京の建物や風俗、博覧会などを描いた錦絵が紹介されている。

江戸末期から明治にかけて、人々が肌で感じていた時代の変化や大きな事件を題材にした錦絵は、美人画や役者絵、名勝を描いたものとはまた異なる魅力がある。規制のなかで人々の心を代弁しようとした高度な風刺精神に、体系的な整理をしながら学ぶことができる展覧会となっている。