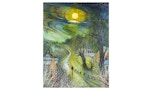第4章「流行り病と錦絵」では、江戸時代末期に何度か大流行を見せたコレラと麻疹を扱った錦絵を展示している。現在は医療や公衆衛生の進歩により、必ずしも危険な病ではなくなったコレラと麻疹だが、江戸時代においては多くの人の命を奪う、原因のわからない恐ろしい病だった。錦絵のなかには、こうした病を避ける病除けや、病気への対処法を伝えるものとしての側面もあった。
安政年間の1858年より大流行して多くの犠牲者を出したコレラは、数日で命を落とすことで大いに恐れられた。このコレラから逃れるために、病除けの錦絵が多くつくられている。例えば、牛のような身体と人のような顔を持つ神獣の白沢(はくたく)を描いた図面は病除けとして重用されたという。

また歌川芳虎画《麻疹養生弁》(1862)は、麻疹にかかった子とそれを介抱する母、それを見守る玄宗皇帝の夢に出てきて病を払ったとされる神・鍾馗が描かれている。さらに本作には食していいものや、行ってはいけないものなどが記されており、病除けとともに病の際の心得を周知する役割も果たしていたことがわかる。