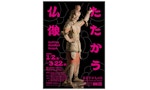第2章「読む!永遠の生命の物語」は、本展の中核を成す章となっている。『火の鳥』の「黎明編」から「太陽編」までの主要12編を、各編ごとに取り上げていく。いずれの編も多くの直筆原稿が展示されており、その数は約400点にも及ぶ。
本章では各編を直筆原稿を展示しながら紹介するとともに、「福岡伸一の深読み!」と名打たれたパネル展示がある。このパネルで福岡は、手塚が参照したと思われる当時の研究と最新研究の比較を行ったり、福岡ならではの学術的な視点に立った物語分析を提示している。
例えば「黎明編」であれば、舞台となっている邪馬台国がどこにあったのか、手塚が本作を書いた当時の歴史研究を、現代の研究を参照しつつ、福岡ならではの視点で語る。

また「未来編」について福岡は、現代のAI社会に深い視座を与えるものと指摘。手塚の時代はまだマンガの中の世界であったAI社会が、2025年現在は現実のものとなっていることを踏まえ、そこから学ぶべきことを分析する。
奈良時代を舞台にした「鳳凰編」は、福岡が初めて読んだ『火の鳥』だったという。エリートの武士と、異形の野生児が鬼瓦を競作する芸術家のドラマティックな物語を、福岡は15世紀のイタリア・フィレンツェのサン・ジョヴァンニ洗礼堂の門扉のレリーフ制作をめぐる、ロレンツォ・ギベルティとフィリッポ・ブルネレスキのコンペティションになぞらえて分析している。

ほかにも福岡は、「生命編」について、クローンにまつわる倫理についての手塚のメッセージを読み取っている。クローンが内包する「コピー元」と「コピー」という関係が必然的に生む支配構造は、現代においても重要な問いといえるだろう。