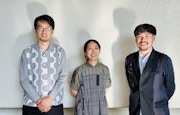文化芸術を生かした地域の活性化、都市の魅力向上を目指し、文化芸術都市としてのさいたま市を創造するために2016年にスタートした「さいたま国際芸術祭」(初回名称は「さいたまトリエンナーレ2016」)。その3回目である「さいたま国際芸術祭2023」の幕が開けた。
これまで芹沢高志、映画監督・遠山昇司(公募)がディレクターを務めてきた同芸術祭。今回のディレクターも公募で選ばれ、目 [mé]がディレクションを手がけることとなった。プロデューサーの芹沢高志は、同芸術祭が「最初から『ともにつくる、参加する』という基本理念でやってきた」としつつ、「見るだけの芸術祭ではないかたちを目指してきた。目 [mé]はそれを徹底的に進めてくれた」と振り返っている。

目 [mé]は、アーティストの荒神明香、ディレクターの南川憲二、インストーラーの増井宏文を中心とする現代アートチームだ。「さいたまトリエンナーレ2016」では旧埼玉県立民俗文化センターの屋外を会場に《Elemental Detection》を発表。池を囲む森のような風景を出現させた。19年には千葉市美術館で美術館初個展となった「非常にはっきりとわからない」を開催。続く21年には、都心に巨大な顔を浮かべる「まさゆめ」を実施し、大きな注目を集めたことは記憶に新しい。
今回のテーマとなるのは「わたしたち」。一見ありふれたこの言葉について、目[mé]のディレクター・南川はこう語る。「気候変動や社会格差など様々な課題が取り巻くなか、いかにわたしたち自身を見つめ直すことができるか。日本を代表する生活都市さいたまから世界をとらえ直す機会につなげたい」。

今年のメイン会場は 「旧市民会館おおみや」。1970年に完成し、多くの人々に親しまれた同館だが、2022年3月の閉館以降は使用されていなかった。芸術祭開催に伴い、ふたたび命が吹き込まれたかたちだ。会場は「タイムベース」という考えのもと、会期中につねに変化し続ける構造となっており、「鑑賞者が『その日その時、そこにいること』を選んだ行為によって固有の鑑賞体験が生まれる芸術祭」(南川)が目指される。
メイン会場の参加作家はアーニャ・ガラッチオ(アーティスト)、イェンズ・パルダム(電子作曲家)、伊藤比呂美(詩人)、今村源(美術家)、エム・ジェイ・ハーパー(ダンサー・振付師/ジャマイカ)、L PACK.(アーティスト)、ジム・オルーク(音楽家/アメリカ)、沙青(映画作家/中国)、白鳥健二(写真家)、谷口真人(アーティスト)、テリー・ライリー(音楽家)、平尾成志(盆栽師)、ミハイル・カリキス(アーティスト)、ポートレイトプロジェクトなど多種多様だ。こうした作家の作品をつなぐ「導線」が、本芸術では大きな特徴となる。

会場は透明板とフレームで構成された「導線」が張り巡らされており、空間を分断/接続しながら鑑賞者を誘う。この導線は「窓」のような機能も持っており、これによって窓の向こう側にあるものすべてを「見るべき対象」に変えてしまう役割を果たす。作品と作品ではないものの境界線が、非常に曖昧になっているため、必然的に鑑賞者は様々な物体に目を凝らすことになるだろう。


この導線は大ホールの舞台の横、裏、そして楽屋にも伸びており、舞台裏に歩みを進めた鑑賞者は「見る者」であるとと同時に、客席側から「見られる者」となる。なお大ホールでは連日、音楽やパフォーミング・アーツ、映画上映などの様々な公演が開催され、そのリハーサルや準備の風景も公開される。


導線と同じく、この芸術祭で大きな存在となるのが、各所に点在する「スケーパー」だ。「スケーパー」とは目[mé]の造語であり、「絵に描いたような画家」の格好をした風景画家であったり、まるで計算されたかのように綺麗に並べられた落ち葉であったり、景色の一部になってしまったかのような人やものを表す。パフォーマンスとそうでないものの差、あるいは鑑賞者なのかパフォーマーなのかすら曖昧になるような、境界も無効化してしまうプログラムだ。芸術祭の会場や場所という枠を超えて、日常のなかに新たな視点を与えることだろう。
作品と会場がゆるやかに溶け合いながら、「見る」ことを強く意識させる今回の「さいたま国際芸術祭2023」。そこで得た新たな視界によって、会場を後にした世界のとらえ方はきっと変化しているはずだ。

なお、「さいたま国際芸術祭2023」は、目[mé]がディレクションするメイン会場のほか、3名の市民プロジェクト・キュレーターらが展開する「市民プロジェクト」や、市内文化芸術事業と連携した「連携プロジェクト」などが市内各地で展開される。こちらもあわせてチェックしてほしい。