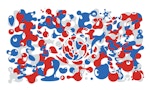なぜ自身の身体を身にまとったのか
──今回の個展での新作《Walking With》(2025)は、自身の身体との不和を感じ続けてきた津野さんが、自分のための服づくりに挑戦した作品です。「重く、動きづらく、ひとりでは少しの距離を歩くのもつらい」服を、自身がまとって歩くという本作をつくることで、これまで自身の身体とうまく付き合えなかったことや、否定してきたことについての考えは変化したのでしょうか。
津野 先ほど、衣服づくりは自分の身体との関係を結び直す経験だった、と言いましたが、その前提には、「それができなかった時間」があるんですよね。これまで、自分の身体を無視してきたこと、隠そうとしてきたこと、否定してきたこと。そうした経験をすべてきれいに「ケアの物語」として回収してしまうことにはどこか無理があるな、という感覚が、ここ数年で強くなってもいました。
自分の身体への態度というのは、決して自分のなかだけで生まれたものではなくて、社会的なまなざし、例えばメディアを通して「美しい身体」という規範的なイメージが内面化された結果でもあると、原因と結果を説明できてしまう部分もある。けれど、その説明を延長するかたちで体との関係修復をゴールとするのは、これまで相当ひどい扱いをしてきた自分の身体をきれいな「ケアの物語」に乗せてしまうようで、どうしても嘘っぽさというか、無理があるように感じています。

今回の個展で「自分の体のために服をつくる」というテーマに向き合ったとき、むしろ自分の身体とうまく付き合えなかったことを大切にしたい、という気持ちが強くなりました。まだ自分には普通に服を着る、身体にまとう、というスタイルは早いと感じています。普段から、自分の体のことを忘れたいと思っているし、その感覚が失われたわけではない。
いっぽうで、年齢のこともあって、自分の体調や血圧のことが気になり始めたり、浦河べてるの家で様々な背景を持つ人たちの話を聞いたりするなかで、身体の見え方が変化してきたのも事実です。心地いい時間、創作活動、ご飯を食べること、人と話すこと、そうしたなにもかもが、体があることによってずっと支えられてきたんだ、という現実を、以前より強く感じるようになりました。
そのふたつの現実があるなかで、「袖を通す」前に、ちゃんと自分の体があるということを感じ直したい、と思いました。だから《Walking With》は、服をつくるというよりも、まず体があることを感じるところから始めたい、という感覚から生まれた作品といえます。
いきなり服を着るのではなく、まずは自分の分身としての服をつくり、それを背負って、自分の重みを感じながら歩く。その関係性が、いまの私にとってはすごくリアルで、ちょうどいい距離感だと思っています。「袖を通す」のではなく、まずは「自分をまとう」ことこそが、いま納得のいく衣服との距離でした。