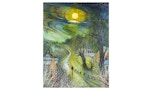生きるうえでの小さな選択の積み重ねが、影響を広げていく
──また、おふたりは、美術館の展覧会や雑誌のインタビューなど、公共の場で発言する機会がありますよね。展示を行うアーティストやデザイナーとして、ある種の公共的な責任を感じることはありますか?
アップリチャード 例えば、デンマークのルイジアナ近代美術館が放送する動画「Louisiana Channel」ではこういったことを話しました。私は世界全体を救えるわけではないけれど、救えないと言っているからといって、試さないわけにはいかないし、できることはするべきだとは思います、と。
ガンパー それは、素材やプロセス、輸送の問題だけではなく、生き方にも関わってくると思います。まずは、誰と仕事をするか、その人たちが何をしているのかを考えることが第一歩です。個人で、または助手やスタッフとどのように仕事をするのか? それ自体は大したことではないかもしれませんが、例えば誰もプラスチックのサンプルを買わない、化学物質が多く入ったものを買わない、といった簡単なことから始まります。私たちは健康的な物を食べるようにしているので、午後3時に疲れ果てて眠くなるようなこともない。ですから、より包括的な視点で考え、生活することだと思います。解決策も多岐にわたりますから、そうすることで、多くの人々に影響やインスピレーションを与えることができるのではないかと考えています。なぜなら、気候意識を持った生活についての、極端に堅苦しく説教じみたやり方ではないから。たったひとつの「純粋」な正しい方法があるわけではないんです。
──仕事をするうえで、絶対に越えられない倫理的な線はありますか? 例えば、大手化石燃料会社があなたの展覧会をスポンサーしたいと言った場合、かなり悩みますか?
アップリチャード 確実に熟考すると思います。でも、同時に別の考えもあって。まだ完全に考えをまとめきれてはいませんが、例えば、そういった大企業からできるだけ多くのお金を引き出すべきではないかとも思うんですね。なぜなら、彼らは莫大な利益を上げていて、それがどこかに流れているから。そのお金をもっと面白い、あるいは批判的なことに使うべきではないかという問いはあります。現代アートの世界はつねにこういった矛盾に満ちています。みんなそれを黒か白かのように装っているけれど、現実はそうではありません。
──そもそも「きれいなお金」なんて存在しませんしね。
アップリチャード ええ、ほとんど存在しないと思います。それでも、とても難しい問題だし、慎重な判断が必要だなと。
ガンパー 一定の限界はありますよね。スタジオではこういった話を時々しますが、これまではそこまで大きな問題にはなりませんでした。振り返ってみると、以前に作品を販売した相手のなかに、いまでは販売したくないと思う人が1〜2人いるかもしれませんが。