「気候危機とアートのシンポジウム アートセクターはどのようにアクションを起こせるか」レポート
2024年7月27日、代官山ヒルサイドプラザにて、気候危機とアートのシンポジウム「アートセクターはどのようにアクションを起こせるか」が開催された。
このシンポジウムは、環境や気候科学の研究者や芸術関係者の基調講演、パネルディスカッションを通して、今後、アーティスト、美術館、ギャラリーやアートスペースなどをはじめ、芸術に携わるあらゆる人々が、気候危機対策の実践者となることを目指し企画された。
ゲストスピーカーに迎えたのは、環境社会学の専門家である茅野恒秀、森美術館館長・片岡真実、十和田市現代美術館館長・鷲田めるろ、Yutaka Kikutake Gallery代表・菊竹寛、ヤマト運輸株式会社(美術)コンサヴァター・相澤邦彦。AITのロジャー・マクドナルドは、アートと気候危機の世界の動向を紹介。そして、クロージング・パフォーマンスには作家/アーティストの小林エリカが出演した。
また、会場では、音楽家・安永哲郎のセレクトによる環境音楽が流れ、オーロラから発せられる電磁波や、キノコの生態信号、流氷の摩擦音などを記録した音源の数々を紹介。物理的にも感覚的にも人間がアクセスしづらい自然界の音を探求した世界各地の研究者や音楽家の実験的な試みを感じられる機会となった。
地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した
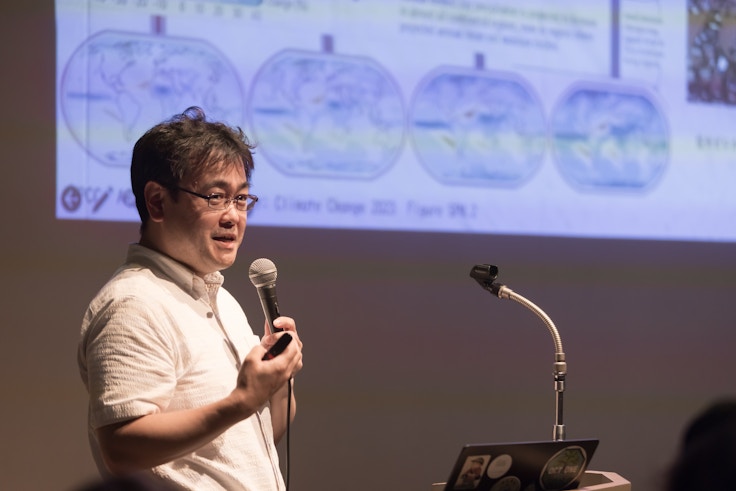
猛暑日となった当日。AIT理事長・塩見有子による開会挨拶のあと、信州大学人文学部准教授の茅野恒秀の基調講演からシンポジウムはスタート。茅野は環境問題について社会学の立場から研究をしているほか、信州大学と信州アーツカウンシルが連携し、文化芸術の視点から気候変動や地球環境の課題を見つめ、県内の様々な取り組みを学ぶ「Shinshu Arts-Climate Camp」という企画にも参加している。
まず、国連のアントニオ・グテーレス事務総長の「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した」という恐ろしいフレーズとともに、上昇を続ける平均海水面温度の推移データを交えた地球温暖化のメカニズムのおさらいから。

自然生態系が吸収可能な量以上に、人類が化石燃料を消費することによって二酸化炭素を放出し続けてきたことが地球温暖化の原因であることは、改めて理解しておくべきだろう。そして、生態系の吸収可能な範囲に二酸化炭素排出量を留めようという試みが、カーボンニュートラル。また排出量を吸収量と相殺して正味ゼロを目指すことを、ネットゼロエミッションと呼ぶそうだ。
どのようにして、カーボンニュートラルな社会がデザインできるのか。ヒントはコロナ禍にある。世界的に人々の行動が制限された2020年。にも関わらず、二酸化炭素排出量はわずか5.4パーセント減だったそう。「つまり、制限=我慢ではダメ。生活や社会構造自体の変革が必要なんだ」と茅野は言う。

このままいくと未来はどうなってしまうのか。 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change/国連気候変動に関する政府間パネル)の報告書によれば、2100年時点で平均最高気温は4°C以上上昇するとも言われている。「ブ ラックジョークのようだが」と前置きし、今年の記録的猛暑も未来から振り返れば今世紀でもっとも涼しい夏だった、という可能性があると茅野は指摘した。



















