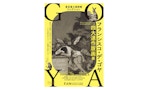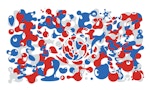36歳で吉川はアーティストとしての活動を始めるのだが、それが感情的な表現を一切排した客観的な外観と数学的な構成を特徴とするコンクリート・アートの領域であることは、ミューラー=ブロックマンによる中立性を志したグリッドシステムの理念と通ずるものを感じる。そしてデザイナーからアーティストへ移行した彼女の手つきから見えてくる普遍性に、ミューラー=ブロックマンと公私ともに行われた対話を想像する。二人がお互いに何に惹かれ合ったのかと勝手に推測するならば、それは社会に対するまなざし、理念の根っこだったのではないだろうか。
彼女は次第にデザインの仕事から離れていくのだが、『shizuko yoshikawa』によれば、それは絵画の領域が男性の言説によって構築され、理論が文化的・実存的手掛かりとなってゆく芸術分野で自立して生き延びるために必要なことだったという。理論的発言を控える女性芸術家たちの歴史は周縁を進まざるをえなくなり、フェミニスト的女性芸術家たちが男性に占領されていない領域へと向かういっぽうで吉川は、例えば私的で身体的な領域での問いかけによって家父長的な構造に揺らぎを起こすような芸術に吉川は向かわず、コンクリート・アートの領域にとどまった。日本の女性の在り方を引き受けなかった彼女にとっては、母国に帰国しなかったという事実自体がすでに大きな表現だったのかもしれない。「この展示は彼女の里帰りである」と言ったラース・ミュラーの言葉に、吉川の体重をずしりと感じる。


作品に次第に見られるようになってゆく、陰翳礼讃のように繊細な光と影による色調は、自分のアイデンティティを探して必死に掴もうとする吉川の切実さを見るようだ。日本から遠く離れたスイスで、彼女が彼女であるために、デザイナーではなくアーティストを選び進んだ道は、吉川が自分は何者であるのかを問い続け、かたちにし続けた道だったのではなのではないかと想像する。
そして、感情的な表現を一切排し客観的な外観と数学的な構成を特徴とするコンクリート・アートの領域で、彼女の表現はどんどん主観的でポエティックになっていく。とくにミューラー=ブロックマンが亡くなった後の作品では、突如として情緒的で個人的な心情を表現している。そして驚いたのは最後の部屋に展示された、晩年の作品で、そこにはもはやグリッドさえも感じない、自身の身体と欲求に任せたかのような彼女の自由な躍動があり、すべてから解放されたかのような吉川静子がいた。


展示空間の最後の部屋には小さく区切られた空間があり、そこにミューラー=ブロックマンの展示がある。日本における認知同様に私自身の認知にも偏りがあったためか、こんなふうにパートナーの彼の展示が小さくまとまっていること自体が新鮮だったが、吉川の展示を見終えた後に彼の展示を見たことで、この空間の比重がとても自然なもののように思えた。そこには彼が吉川と出会うずっと前の、青年期の絵画的な仕事や、グリッドのない自由で躍動感のあるレイアウトがあり、吉川と出会って彼女がアーティスト活動をするようになった時期につくられた見慣れぬ彫刻作品があった。その後、彼がグリッドシステムを構築したことは周知の通りだが、彼の晩年の仕事が再び自由で有機的なレイアウトに戻っていたことは、人は老いると再び心がプリミティブになっていくという至極素朴で愛おしい側面でありながらも、吉川が彼女自身のアイデンティティを必死に掴もうとし、社会から求められるものを引き受けず、「自分だけの部屋」かのような「自分だけの美学」を構築しようとする姿に、影響を受け続けた結果なのではないかと感じずにはいられなかった。私たち夫婦はパートナーです、という吉川の言葉が、この展示でやっと公平な質量とバランスで伝わってくるような気がした。

- 1
- 2