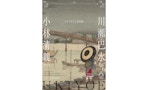私的な経験と公共性の葛藤
このように本展は、自然と人間とを見つめる5名の作品が緩やかにつながって、会場全体が一続きの絵巻のように展開する充実した内容だった。だからこそと言うべきか、筆者が引っ掛かったのは、キュレーターの金澤が上海のロックダウンの渦中に発信したSNSの投稿文が会場に置かれていたことである。その言葉たちには、「春望日記」という題が付されていた。

これがアーティストの作品であれば、何もSNSというプラットフォームやそこで交わされる言葉、情報を題材・素材にすることは珍しくない。しかし本展で展示された作品や資料のうち、もっとも無加工で生っぽい素材が企画者自身の声だったことに、少なからず戸惑いを覚えたのだ。それは、筆者が公立の美術館で働いてきた学芸員だからという個人的な事情、もしくは私情に起因する戸惑いだと自覚する。あくまで私見だが、学芸員はなんらかの専門や関心を持つ個人であるのと同時に、あるいはそれ以上に、公の組織の人間であることを求められる局面がある。そのためか、少なくとも展覧会という公的な場でありのままの言葉をつぶやいたり、悩み葛藤し喜怒哀楽する姿をさらけ出すことは、ゼロではないにせよあまりない。括弧付き「公共」の感覚をいつのまにかインストールしてしまった筆者にとって、キュレーターである金澤が自身の私的な経験を私的な言葉でひらいたことに驚きと戸惑いを覚えたのは、このような理由による。「これってありなのか?」と思ったのだ。
「私」の思いや経験を「公共的」に見せて語る方法やテクニックはいくらでもあるなかで、あえて生の言葉を置いたのには理由があろう。ひとつは、展示の出発点をクリアに伝えるためである。もうひとつは、展覧会の射程を私的な領域からより大きな時間軸へと広げるためだ。
「春望」という本展のタイトルは、中国唐代の詩人・杜甫の詩に由来する。「国破れて山河あり」から始まるこの詩は、戦乱で荒廃した都市・長安の景色と、変わらぬ春の自然とを対比させながら、人間社会の不条理や家族への追慕をうたったものだ。この詩のように、私的な経験を普遍化する態度は5名の作家に共通する。例えば方巍のエネルギーに満ちた絵は、彼とUMAが子供たちを連れて上海から奈良へと移り住んだ経験が描かせたものだし、谷川の彫刻は彼女が日々を過ごすなかで感じた季節の表情や、移り変わる時間をとらえることから出発する。近くて遠い、小さくて大きいというスケールの往還が5名の作品や会場全体から感じられたように、本展が示したのは、小さく近い私的なものと、大きく遠い普遍的なものとのあいだを行き来する人間の想像力だ。
公共性とは曖昧なものだ。この言葉や制度のなかには、結局は極めて私的な経験や思考が潜んでいる。だからこそ公共性という大義名分でコーティングされた感情や欲望は、ときに無慈悲な暴力になって誰かの言葉を奪う。金澤が綴った『春望日記』は、この公共性の不確かさに抗う決意なのだろう。本展は、私的な経験が持つ普遍的な強さについての展覧会だ。そのためだろうか、私がこの展覧会を振り返り思い出すのは、友人とともに町屋を歩き、階段を昇り降りし、畳に座って目の前に佇む作品をじっと見つめた、極めてパーソナルな時間そのものだ。同時に、やはりこうも思う。私たちは、自らの言葉で話さずにはいられないのだと。
参考文献:根本美作子「近さと遠さと新型コロナウィルス」村上陽一郎編『コロナ後の世界を生きる』2020年7月、岩波書店。