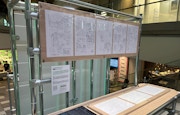文化庁による「文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業」は、メディア・アート、ゲーム、アニメーション、マンガ等の若手クリエイターの創作活動を支援する事業だ。 2011年度よりスタートしたこの事業だが、2023年度からは文化庁メディア芸術祭の終了を受けて規模が拡充。成果発表イベント「ENCOUNTERS」(〜2月25日)も開催されている。東京・表参道の表参道ヒルズ地下3階の「スペースオー」と吹き抜け大階段で開幕した本イベントをレポートする。

本イベントは、スペースオーでの「成果プレゼンテーション展」と、吹き抜け大階段での特別展示で構成される。「成果プレゼンテーション展」では、今年度採択されたクリエイターの作品制作の成果及びワークインプログレスを紹介するとともに、過去の採択クリエイターの作品も招待展示される。
今年度採択された作品のなかから興味深かったものを紹介したい。視覚文化をモチーフに作品制作を行う原田裕規のWaiting for プロジェクト《Home Port》は、「レンダリングポルノ」と称される、現実逃避的なCGの風景の特徴をアートとして再解釈。原田が「アンリアルな風景」と呼ぶCG風景を平面作品として出力した。

映像と写真を同時に行き来することで、新たな視点を模索するネメスリヨの《ONCE》は、複数の異なるループ映像を再生し、それを繰り返すなかでの重なり合いや調和を模索する作品だ。さらにタッチスクリーンを触れると映像を動かすことができるが、スマートデバイスのタッチパネルとは異なり映像そのものの質感や重さを感じせるような動きが生まれている。

美術家・アニメーション作家の副島しのぶの《彼女の話をしよう》は、殺された女神の身体から食物がもたらされるという、ハイヌヴェレ型神話を題材にした短編アニメーション。土や米、芋、肉、 などをアニメーションで動かす本作のコンテや設定資料、人形などを会場で見ることができる。

布施琳太郎の《海の美術館》は、美術館にとっての「建築」を再考するプロジェクトだ。インドやフランスにおけるル・コルビュジエ建築の現地調査を軸としながら、自作のゲームを通じたコミュニケーションによって現地の専門家との対話=リサーチを行う。またル・コルビュジエが美術館建築の構想を始めたのと同時期におぞましい建築を小説に描いたH・P・ラヴクラフト、磯崎新のプロセスプラニング論などとの比較を通じ、新たな美術館建築のプロトタイプを提示する。本作は3月12日から国立西洋美術館で開催される「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?——国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」に出展される布施作品のスタディとなるはずだ。

自一他の境界、人間一非人間の境界への問いかけを続ける花形槙の《A Garden of Prosthesis》。人間中心主義的な関係を反転し、新たな関係をかたちづくるために「作庭」をパフォーマンス、およびインスタレーションとして展開した。人工物、AI、人間の肉体などが混じり合い、庭と身体が一体化する瞬間を探っている。

過去の採択クリエイターの作品も佳作がそろう。GengoRaw(石橋友地+新倉健人)による、X(旧Twitter)のリアルタイムのトレンドワードから、AIが言葉を収集し、詩をつくり続けるシステム《バズの囁き》。異なる性格付けを施した3台のAIが、それぞれ独特の詩を読んでいる。

また、映像作家/アーティストの吉開菜央や、アニメーション作家/イラストレーターのぬQの過去作の特集上映、榊原澄人のアニメーション作品《飯縄縁日》の展示なども行われている。

加えて、文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業は作品そのものではなく、展示やプロジェクトの発表を支援する「発表支援プログラム」もある。こちらはパネルを中心とした展示となるが、クリエイターたちのユニークな発想に注目したい。
そして、吹き抜けの大階段では特別展示として、「メディア芸術」の歴史的な作品を紹介。磯光雄、あさのいにお、西村ツチカなど、気鋭のクリエイター8組の創作の裏側にあるコンセプトメイキングや表現技法、制作プロセス等を紹介している。

文化庁が提示する「メディア芸術」の現在形を知ることができる成果展。領域を横断的に制作者たちの作品や思いを知ることができる機会となっている。