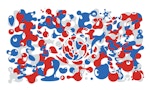――まずは「心霊写真/ニュージャージー」というタイトルから入りたいと思います。
いままでぼくが取り組んできた展覧会は、例えば「ラッセン展」(2012)や「心霊写真展」(2012)のように、1展覧会=1ワードで構成することがほとんどでした。それに対して、今回は「心霊写真展」と「ニュージャージー展」という2つの展覧会が同じ会期と会場を共有しているようなイメージで、「心霊写真/ニュージャージー」というタイトルを付けています。
そもそも、ぼくはいままでアートとしての写真には興味を持てないでいたんですね。そのいっぽうで私生活では写真に依存していて、多い日には1日で500~1000枚ほど写真を撮ることもあるくらいです。それほど写真と強く結びついていながらも、どうしてもそれ自体が作品になるとは思えないでいました。この感覚を言い換えれば、写真とは、此岸にある生者の道具ではなく彼岸にある死者の道具であるような感じです、この感覚に一番近いカテゴリーが「心霊写真」でした。

もし世界のどこかに「本物の」心霊写真があるとするならば、「作者が特定できないこと」が条件になると思います。どうしてかというと、作者が特定された時点でその心霊写真は偽物であると認定されてしまうからです。つまりここで「心霊」と言われているものは、心霊「が」写っているという意味ではなく、心霊「による」写真という意味で、撮影する側を定義しているのです。
この撮影する側の分類において、「家族写真」は「心霊写真」に並べられると思いました。実際に心霊写真の多くがこうした写真の中から「発見」されていますし、普段ぼくが撮影している写真の多くも「家族写真」や「記念写真」などに近い用途で撮られている。だから、こうした幾つもの種類の「~写真」が横滑りしていくような空間をつくってみようと、すでに取り組んでいた「心霊写真展」に対して「記念写真展」とでも言うべき「ニュージャージー」をぶつけるという構成を思い付いたんです。

手に取れるかたちで展示された。
――原田さんが最初にキュレーションした「ラッセン展」では、ラッセンの絵を現代美術風のフレームに入れ、その隣に現代美術として扱われる作品を公募団体展風のフレームに入れて並べるという方法を取っていました。原田さんの継続的な問題でもあり、本展ではタイトルの「/」にも表れているような、通常併置されない対象をぶつけていく方法論はどのように生まれたのでしょうか。
ぼく自身の来歴と関係する話になりますが、もともと実家の一室にラッセンの絵が飾ってあって、たまに家族でヒロ・ヤマガタ展なんかにも行くような環境だったので、漠然と「美術」とはそういうものだと思っていました。それが中学生の頃に洋画にハマり、高校に進学する頃には現代美術と出会うことで、そうした認識が段階を経ながら覆るということがありました。
ただ、当時はとにかく情報に飢えていたので、現代美術だけでは満足できず、地元の美術館やギャラリーはもちろん、美術部が活発に活動していそうな高校の文化祭からデパートの催し物など、「展」と名が付くものには片っ端から足を運んでいました。それで公募団体展やら現代美術やらラッセン展やらをカオスに鑑賞するようになってきて、そのときにそれぞれの「美術」に合わせて身体が変化してしまう感覚に快楽を見出すようになっていったんですね。その際にメタな視点でそれぞれの展覧会を相対化するだけでは面白くなくて、ひとまずそれぞれの序列を保留にした上で、個々の空間にベタに没入する感性が必要になると思いました。そのようにひたすらラディカルに受動的になってしまえという態度が、最初に企画した「ラッセン展」(2012)では顕著に表れていたように思いますね。

フィルムアート社、2013
――メタとベタのパーセンテージはどれくらいなのでしょうか。
どちらかというとベタさが多めです。ぼくがいま住んでいる自宅にもラッセンの絵が飾ってあるのですが、基本的に紙幣や壁紙みたいにフラットな画面なので、一瞥するだけでは視線が跳ね返って鏡を見ているような感覚になります。それでもめげずに眺め続けていると、それまで跳ね返ってきていた視線がゲームの一人称視点みたいにすっと奥に入り込む瞬間がある。こういう体験を導入するために、過剰なフレーミング(額装)をキュレーションや作品として出すことをしています。
どうしても「フレーム」というと、作品でなく制度の話として認識されるところがありますが、ぼくにとって両者の区別はそれほど明らかではありません。なぜかというと、デュシャン以降「言語ゲーム」と化した現代美術にとって、芸術作品の「外部」にある台座や額縁こそが作品の本質を規定するものであると考えられるようになりましたが、そのことがあまりに自明視された現代のゲーム的な世界においては、もはや台座や額縁の操作も物語を紡ぎ出す「絵の具」として普通に流通しているからです。そういう意味では、現代美術において「作品」や「物語」という概念は一般的な意味よりは少し引いたところに設定されていて、そこに再度作家的に介入できないかなと考えています。
たとえば今回の展覧会では、デュシャン的なレディメイドの手法を「署名のない写真」に適用することで生まれた「ファウンド・フォト」という制度に注目しました。これは、署名のない/あるいは署名が見えづらい「素人写真」にアーティストが署名を上書きし、自らの作品として出し直すという点で、収奪的で問題のある制度なのですが、これまで現代美術というゲームのなかでは深く問題視されることはありませんでした。

このことに対して、ゲーム内の同じ階層から言語を繰り出すだけではインパクトは与えられないだろうなと思ったんです。そこで、こうした行為をまずは過剰に自ら反復してみようと、できるだけ多くの作者不詳の写真を集めることにしました。
そのほとんどは、さまざまな理由から「捨てられるはずだった写真」です。収集を始めて1年後には、およそ1万枚弱の写真が集まったのですが、これらの写真を1枚1枚できるだけ丁寧に見ていくうちに、知らない人たちの存在が脳裏に焼き付き始め、会ったことも声も知らない人が夢に登場するなどして、トラウマ化するに至ってしまった。
ファウンド・フォトという手法は、その「収奪性」から批判されるのがセオリーですが、それ以上に、アート・ワールドの駒として写真を体よく運用するために、イメージが本来持っている、トラウマを与えかねない暴力性を隠蔽していることにこそ、その罪の本質があるのだと気が付きました。そうであるならば、この暴力性を解放することこそが、人間性を排除する方向に突き進むアート・ワールドに対してより強いインパクトを与えられると考えたんです。「心霊写真」というカテゴリーはそのためのステップとしてとらえています。

――ラッセンの絵における壁抜けのように、作者不詳の写真のなかへと入り込み、そしてそこで大量な非言語的要素を受けながら、新たな人格を獲得していくようです。
ラッセンにおいても心霊写真においても、一度そのなかに「入り込む」という作業がとても重要です。そしてこの作業から得られたものを作品化しようと思い、今回は《百年プリント》という新作をつくりました。
これは、1980年代にサクラカラーから販売されていた「百年プリント」のDPE袋の複製品と、黄ばませることで実際には新しいのですが古く見せた写真、黄ばむ前の写真の像が写されたネガ、そして「ニュージャージー通信」という手紙をセットにした作品です。この写真を撮影したのはぼくなんですが、自分自身、これらの写真が先ほどお話しした写真の山から発見されたものであると「思い込み」、写真を撮ったであろう人の気持を想像した文章を書き、それと組み合わせた写真によって構成されています。

誰しも最古の記憶を辿っているときに、じつはそれが写真によって事後的に捏造された記憶だったと気づくことがありえると思います。そうした捏造力は、大なり小なりすべての写真に潜在しているものなので、写真からそれを無理やり引き出すような感覚で「写真に内在する人格」を立ち上げてみようと試みました。
今回の展覧会では「作者が分からない写真」をすべて「心霊写真」と呼んでいたのですが、1万枚弱集まった写真を会場に置いていたので、そこには「トラウマを与えかねない暴力性」があふれることになりました。それに対して、こうした「暴力性」をただ露わにするだけでなく、再び人の手による「作品」に結晶化するための布石として、《百年プリント》を展覧会のハイライトに持ってきたんです。
――作者不詳の写真から獲得された人格を通じて、作者不詳の作品制作を行うということは、自身のなかのアーティスト像を心霊化するということにもつながりますね。
「アーティスト像」自体が、先ほどお話ししたように何かを克服する過程で立ち上がるものだと思います。そのとき「克服」と言うからには、その対象は「自身よりも大きい何か」になることが多いのですが、今回のぼくにとってそれは、もはやほとんど非人間化しつつある「アーティスト」という存在そのものだったのかなと思います。

先ほど言語ゲームとしての現代美術について触れましたが、それが高度化した現代においては、アーティストそのものも──たとえばラッセンのように──需要に応える記号としてうまく社会を「サーフすること」がもっとも正統な態度になりうるという見立てが発動します。
しかしそうなってくると、それは生身の身体を伴う人間でなくとも可能になることだとも言えるんです。そうした状況に対して、アーティストが再び生きた身体を取り戻すためには、高度化した言語ゲームを一旦は内面化しながらも、同時にそれ自体をひとつの物語世界として探索するプレイヤーとして、身体を二重化する必要がありました。そのためには、従来的な「作品」も「批評」も「キュレーション」もすべて動員した空間をつくる必要がある、というのが、ぼくにとっての克服の方法論です。
――「つくる」という行為は、主体的であるか否かという問題よりも、あらゆるものを総動員して行われるものだと思います。そうした意味でアーティストの主体性というのはすごく微妙なところにあり、ゆえにもしかしたら霊媒的であるのかもしれません。原田さんは、そうしたプロセスそのもののなかに身を投じているように感じます。
文字通り「身を投じる」という作業で、一番重要視しているのが「実際にラッセンの絵を部屋に飾って毎日眺めること」であったり「実際に大量の写真を集めてその気配と匂いに囲まれてみること」だったりするんです。そうした時間のなかで、自分の身体に何が起きるかという観察と実験が、いまのところのぼくの制作の中核にあるなと思います。それとことさらに自分を「アーティスト」として強調しないのは、いまや一般的にみなされる「アーティスト」の役割が限定され過ぎているので、たんに不便だなと思うことのほうが多いんです。
――原田さんの仕事が興味深いのは、「ラッセン」「心霊写真」と、一般的にどこかニッチなイメージを持たれているにしても、潜在的な領域が非常に広大な対象を選択しているというところです。そうした総量に対するバランス感覚はどのようなものなのでしょうか。
できるだけ大きな領域を扱いながらも、それらが身体化して「自分の問題」として扱えるところは、すべて具象的でときにニッチなモチーフにならざるをえないからじゃないかと思います。
その「大きさ」に関して言うと、一般的にアーティストが他領域の何かを扱おうとするとき、「ピックアップ」という言葉が暗示している通り、自らの手の内に収まるものを扱うことが多くあります。その一例が先ほどのファウンド・フォトで、それも「素人写真」という「ピックアップ可能なもの」であるからこそ一見成り立っているように見えているだけで、実際にそこにある「イメージそのもの」に素でぶつかってしまうと、そもそも表現として成り立たなくなってしまう。でも、そういう「成り立たなさ」こそが大事だと思うんです。
例えば、毎日ラッセンの絵を眺めているうちにベタに感動できるようになってきたり、日々知らない人の写真を眺めているうちに、その人と会ったことがあるのかないのかもわからなくなってくるようなときに、自分にはそのイメージの大きさを扱うことなど到底できないなと思うと同時に、その大きさの実感がある程度正確に掴めてきます。
そういった意味で、すでに誰かによって掘られた軌跡であったとしても、途中で放置されていることのほうが多いので、それを「過剰に」掘り進めるということであれば、いまもその余地はそこらじゅうに残っているなと思っているんです。
――自分自身のスタンダードすら変化させる、書き換え可能な価値観の極致という感じがしますね。
「過剰に」何かを進めるということは、もちろん身体にも精神にも負荷のかかる作業です。なので、自分の人格や価値観を書き換えなければいけない局面もあります。でもこれはそんなに悲観的な作業ではなくて、むしろそういう価値観の書き換えにはとことん受動的になってしまったほうがスリリングで楽しい、というのがぼくのスタンスです。

――原田さんの作品はドキュメンタリーですらなく、フィクションとリアルの対比もない、そのことで書き換え可能な領域のありかを示しているのだと思います。
今回の展覧会では何度も「裏切り」の場面をつくってみました。とくにドキュメンタリーには、広大な「わからない領野」に「事実」という名のフィクションを与えることで、それを見る人から不安や疑念を奪ってしまうという側面がありますが、それと反対のことをしてみようと思ったんです。
それはいくら経っても「〜である」という確信だけが得られないような感覚で、この不安はそもそもぼくがひとりで写真の山に向き合っていたことに感じていたものでした。それがおそらく、いわゆる「ドキュメンタリー」が与える安心感とは真逆のもので、どこまでも意味を獲得することが抑圧されてしまうことによって、次第に人が物語を欲望するようになり、たとえば心霊写真という、宗教や芸術や文学の間にあるようなものが生み出されたのかなと思いました。作家としては、そういう潜在的な物語をどんどん解放していきたいと思いますね。