蓮沼くんへ
無駄な10連休があったおかげで、この2週間は大垣でぼんやりできました。この街で僕の生活に欠かせない田中酒店に久々に行ったり、y’KUNIEDAという自家製天然酵母パン屋さんに行ったりしてました。僕はそもそも、そんなにパン派ではなかったと思うんだけど、ここのパンはいいです。プロヴィンチアがサイコー。日本酒とパンでぼんやり酔ってました(もちろん、暦通り働いているんだけどね)。
とくに田中酒店は、僕にとってはギャラリー代わりみたいなもので、行くと主人が、冷蔵庫にしまいこんである日本酒について、素材から製法、その土地の水のことから、今年の状態、杜氏や経営者の人柄から歴史まで、ずーっと話すんです。ときには試供品をいろいろ振る舞ってくれるんですよね。最初はサービスなのかと思っていたんだけど、こちらもいちおう批評とかする人間だから、あーだ、こーだ言い返すもので、実験台にされてるな、と気がつきました。今回も、某銘柄の、5種類も酒米を使った大吟醸は、お米の味が舌の上で変化して喉越しの余韻まで驚くべきものだった。すこし甘いけど。で、思わず「すごい。買います」と言ったら、「あー、じゃあ今度入れとくから、今日は他の持ってって」と言われ、試供してくれたのに売ってくれないのです(笑)。

これはもう笑い話ですが、こういう差異に注目している人との会話というのはね、アートの話そのものですよね。こういう人が、がんばっているあいだは、文化が展開するチャンスがこの街にもあるのではないかと思っています。でもやっぱり足りないのは音楽かなぁ、と、この往復書簡の最初の頃に書いたことにつながりつつ。
さて、昨日もらった蓮沼くんの書簡に質問がありましたね。「音楽と美術が接近していた時代」について、これは1960年代のこととしてとらえると、現実にどうであったかと少しズレるかもしれないんだけど、東野芳明に即して答えてみたいと思います。
東野は、1945年以後、第二次世界大戦前後、つまり敗戦によって日本社会の激変と、ヨーロッパ中心からアメリカ中心へと文化の変化を意識しました。これは別に東野だけじゃなく、この時代の文化人の多くが考えたことではあります。そのなかで東野が、50年代後半、60年代前半、ヨーロッパ、アメリカをめぐって自覚していくことって、40年代後半、戦争直後、勝敗と関係なく、アメリカが世界に進駐して、例えばコカ・コーラを子供時代の記憶にしている人たちが世界中にいるとか、マス・メディアの登場だとか(ラジオもテレビもアメリカが世界中で仕掛けた側面がある)、東野自身も含め、それぞれの文化圏で「アメリカ」的なものを内面化して、共通言語とした同世代の作家たちとの出会いなんかがあるわけですよ。つまりは芸術の変質で、ジャスパー・ジョーンズやロバート・ラウシェンバーグの作品を見て、「こんなのも芸術だったのか」とか、ジョン・ケージや一柳慧を見て、えーって思ったり、日本でネオダダや小杉武久を見て驚くわけだよね。その都度「自己崩壊」に次ぐ「自己崩壊」してる。
歴史的には、それぞれの分野の定義が問われ、還元主義的にジャンルの区別が見えなくなって接近したという言い方をすべきなのかもしれない。けれど美術批評家、東野芳明的には、美術も自己崩壊、音楽も自己崩壊、建築も自己崩壊、映画や演劇も自己崩壊して、廃墟感というか、全部が芸術という更地に佇んでいるという、清々しい接近を感じたのだと思う。僕自身の解釈が多分に含まれていますが、美術と音楽が似てきたという意味ではなく、同じ場所から再スタートだ、みたいな「接近」が起こっていたと考えたいです。何か還元主義的な接近ではないけど、気がついたら共通の価値観としてアメリカが刷り込まれてるけど自国は廃墟みたいなね。少しいい加減というか、開き直りみたいな感じですが、アメリカを経由して理解する自国の更地に立った風景が可能性に満ちていると感じて行動を始めた、ってことだと思いますね。なにかいま現在、僕にはこれと似た感覚があります、ただの直感ですけど。この時代の芸術状況としてなのか、僕が東京から大垣に来て、ということなのか、それさえ判然としませんけど、考えてみたい。
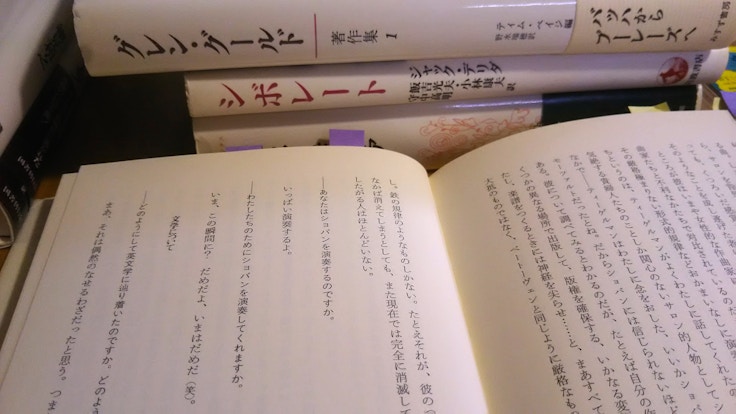
この往復書簡の自分なりの意義として「再配置」と書いたわけですが、何を再配置しているのかというと、例えば、蓮沼くんが何をどう考えたのか一柳の《IBM》を再演しようと思うわけじゃない、僕は理由を細かくは知りません。それを見に行って面白かったけど、やっぱりなんでだろう? とまだ考えるわけですよね。すぐに、あれは良かった、悪かったとかいう感じでなく、なんだったのか? とね。そうこうしているうちに、蓮沼くんと直接関係ないけど、小杉さんのことも考え始めていたりするわけです。
それと、今回の「Someone’s public and private / Something’s public and private」も、やはりよく経緯をわかっているわけではないところから、なんだろう?と思うわけですよね。僕としては評価しているのですよ、と断るのもヘンだけどさ、蓮沼くんの活動が面白いと思っています。何がポイントなのかわからないんだけど、歴史が透けて見えるというか、いまと過去が同時に感じられて、考えるべきことがフワッと見える気がするんですよね。だから蓮沼くんを見ていながら、一柳や小杉の影響があるという話ではなく、蓮沼くんのパフォーマンスや思考を通して、僕が過去を理解したり考えるということが起こるのね。きっとそういうオーディエンス、僕だけじゃないと思う。こうした体験を再配置と思っています。
そういう意味では、往復書簡にしては、それぞれのことを突っつき合うような話じゃないところが多くて、それを期待外れに感じている読者もいたかもしれないんですが、僕自身は、蓮沼くんを通じて感じたことを考えるということを繰り返した感じ。随分好き勝手に書く感じでもあり、楽しかったのですが、蓮沼くんが相手でなければ、こんなに自由に考えたり、手紙を書くことはなかったと思って、感謝しています。またこういう機会が持てればと思います。
そういえばアンサンブルの話、もっとする機会があるかな、と思いつつちょっとそれが足りなかったので、少しだけ最後に書きたいと思います。「表現者同士を“分断”しない思考」っていうところに関わるんですが、僕が昨年、名古屋で蓮沼フィルを聴いたときに考えたことって、バルトークの「管弦楽のための協奏曲」のことなんですよ。バルトークとしてはコンチェルト・グロッソを想定していたらしいけど。つまりソリストがいない協奏曲という、たんに「全部平等です」みたいになると、ベートーヴェンの「ピアノ、ヴァイオリン、チェロと管弦楽のための協奏曲」のソロの退屈さみたいになってしまう(これは趣味判断ですね)。
いずれにしても、バルトークにそういう考えがあったかの詳しくないのですが、「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」も2群のオーケストラだったけれど、「管弦楽のための協奏曲」に至って、オーケストラという集団をインディヴィジュアルなソリストの集団として再定義したのだ、という主張を僕は感じています。とくに第2楽章の「Presentando le coppie(対の提示)」、ただただ楽器が並置されて発展や変奏もなく順番に演奏するだけの楽章です。蓮沼フィルが演奏するテリー・ライリー「in C」を聴いてるとき、これを思い出していたのですよ。そういえば、グレン・グールドの「in C」に関するテキストの話をしないままだったね(笑)。またなにかの機会に、どこかで続きを!
2019年5月11日 大垣にて
松井茂























