2020年10月から12月にかけて、「KYOTO STEAM−世界文化交流祭−」の「国際アートコンペティション スタートアップ展」が開催された。KYOTO STEAMが市原えつこや久保ガエタン、林勇気をはじめとする作家と、コラボレーションするデジタルハリウッド大学院、株式会社コトブキや株式会社タウンアート、京都大学iPS細胞研究所などの企業・研究機関を選出。それぞれのコラボレーション作品が発表された。従来の自身の作風に縛られることなく新たな表現を展開している作品も多く、意欲的な企画であることが伝わってくる展示だった。
このスタートアップ展を経て、まず参加企業と研究機関の公募が実施された。集まった数は41。そのリストがウェブに公開され、各企業の情報をもとに111名のアーティストからコラボレーション作品プランが集まった。公募を審査した結果、11本の作品プランが採択され、春にアーティストと企業・研究機関の顔合わせが行われた。企業・研究機関が素材を提供するだけではなく、アイディアや知見も差し出してアーティストを刺激し、コラボレーションが進められた。

今回の取材記事に登場するのは本展に参加する3名のアーティストだ。記憶の再編によるアイデンティティの分有によって「他者の中に開かれる自己」をテーマに制作する川松康徳、テクノロジーを駆使して物質や現象の「芸術」への読みかえを試みる三原聡一郎、「エラー:失敗の行為によって新たな価値観が生まれる」をテーマにミシンを用いて制作を行う宮田彩加。記事前半ではそれぞれの作品制作について個別に、後半では鼎談形式でコラボレーションの可能性について話を聞いた。
川松康徳×理化学研究所植物-微生物共生研究開発チーム
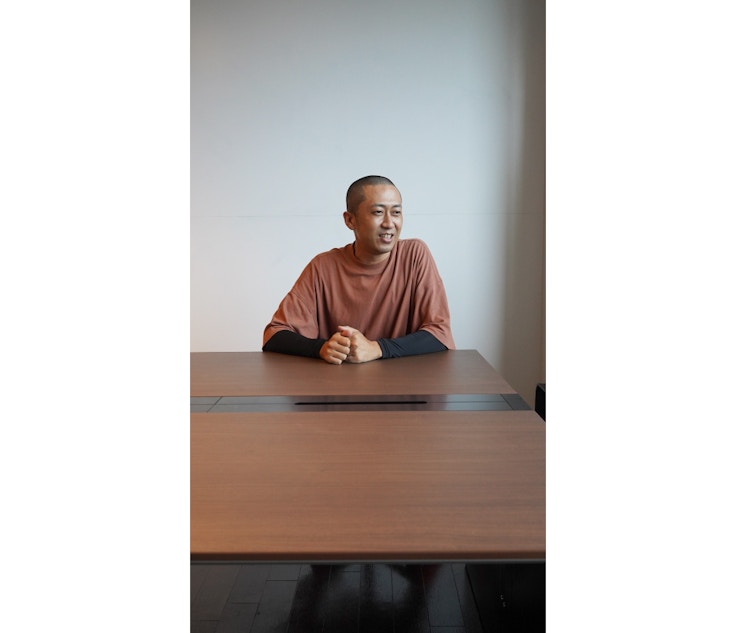
「アイデンティティ」をテーマに、協働者というかたちで移民などをインタビューして作品を手がけてきた川松。ロッテルダムで滞在制作を行ったときに、コラボレートした移民のひとりが植物のセラピーを受けていたことが、今回のプロジェクトのヒントとなった。植物との関係について話すなかで「共生」について考えたことから、理化学研究所植物-微生物共生研究開発チーム(以下、理研チーム)の研究に目が向いた。川松は理研チームの研究内容についてこう説明する。
「アーバスキュラー菌根菌という菌が存在するのですが、これは植物が土壌から養分を取り入れる生態系の仕組みに組み込まれている菌なんですね。植物が単体で存在しているのではなく、根っこが接しているエリアにいるアーバスキュラー菌根菌もその植物の生育には欠かすことができず、それも植物の一部のような状態になっている。その共生関係に興味を持ち、実際に研究する人がどのような知性を持っているのか興味を持ち、対話を通して新しい作品を制作するプランを立てました」。

アーバスキュラー菌根菌の研究と培養を行う理研チームの研究内容は、もちろん川松の思考を刺激しただろう。しかし、直接的に根や菌を作品として扱いたいわけではなく、彼がより興味を持ったのは、理研チームの研究者がその研究をしたことで世界の見え方がどう変わったか、そしてそこにはどのような知性や好奇心が働いているのか、ということだった。
「作品のテーマとして記憶を扱っているのですが、僕はこれまで人間の尺度でしか物事を考えてこなかったので、人間にアイデンティティがあるように植物にも同じようにアイデンティティがあると思い込んでいたし、人間のように主体性があると思ってしまっていました。けれども理研チームの市橋泰範さんの話を聞いていると、それはどうも違うということがよくわかりました。じゃあ植物に記憶があるとしたら、と考えると、それは植物の生態系に存在するのではないか、そこで記憶の循環が起こるのではないかという発想が生まれたんです」。
ロッテルダムで協働した移民のひとりから得た植物セラピーというアイディアが、理研チームとのやり取りによってブラッシュアップされた。植物セラピーを受ける植物学者のインスタレーションを作品として発表する予定だ。
三原聡一郎×mui Lab株式会社

「環境の状態やその情報をセンシングして作品に用いることがあるのですが、応募時期がちょうど新型コロナウイルスによるパンデミックの最中で、空気に興味がありました」と語るのは、三原聡一郎。コロナウイルスから身を守るのか、共存するのか。どんな状況でマスクをすべきか、ウイルスは今後どうなるのか、という世間の空気感。mui Lab株式会社とのコラボレーションで作品プランを立てた経緯を次のように話す。
「mui Labさんは、Calm Technologyというコンセプトを掲げているのですが、世の中ではものすごいスピードで技術革新が起きて活発にコミュニケーションが行われるなかで、もう少しゆっくりと柔らかい、気楽なコミュニケーションがあってもいいんじゃないか、という視点で製品開発をしている企業です。温かみのある木の情報端末はミニマルでシンプルなコミュニケーションを成立させるもので、家具の延長とも呼べるようなデザインなので、それをインターフェイスにして作品を手がけたいと考えました」。

コロナ禍でマスクをつける機会が増えたこともプランに関係した。「街の匂いなど、普段無意識で感じていたものが感じられず、生きる実感が微妙に乏しくなっていることを意識していたので、嗅覚にまつわる作品を考えた」という。だが、「香りの作品」ということを強調するものではなく、進歩を続けるmui Labのスタンスと歩を合わせるように、デバイスと体験の開発に取り組んでいる。
「僕もこれまでいろいろな作品をつくってきたのですが、mui Labさんもこれまでの方法論があります。通じるところもありますが、それぞれの経験値を一度全部壊して、そこから何が立ち上がってくるのかに興味があって話し合っています。どちらも経験したことのない場所に向かって、一緒に足を踏み外しもしながらも、和気藹々とコラボレーションしています」。
宮田彩加×株式会社SeedBank

ミシンのプログラミングにあえてバグを加えることで想定外の美しさが生まれることに着目した刺繍作品を手がける宮田彩加。針の動きによって糸が織りなす範囲が広がる様子から細胞の増殖を連想し、エルンスト・ヘッケルの生物標本やMRI画像などをモチーフに制作してきた経緯がある。KYOTO STEAMで企業と協働するのであれば、これまで標本や二次元のデータでしか知ることのできなかった動植物のモチーフを、生きた状態で観察して触れることができないかと考えて株式会社SeedBankを作品プランに選んだ。
「SeedBankさんは珪藻など様々な微細藻類を研究し培養している企業です。ヘッケルの生物標本にも描かれていたので珪藻の存在は知っていましたが、ミクロの世界のものなので実物を見たことはないですし、生態についてもよく知りませんでした。実際に解明されていない点も多いのですが、珪藻の種(たね)のかたちや特性を明らかにし、種を発芽させて培養する仕組みを開発したのがSeedBankの石井健一郎社長で、『珪藻のことをみんなに知ってほしい』というバイタリティを持って活動されている方なので、海にも採取に連れて行っていただいたり、すごく楽しくやりとりさせていただいています」。
刺繍は作業に時間を要する。そのためにできるだけ今年春から初夏にかけて頻繁にミーティングを重ね、後半は制作に費やしたいという希望も石井社長は快諾してくれた。海の泥のなかにいる珪藻の種を採取する器具も社の顧問を務める研究者が開発しており、研究に対するクリエイティブな取り組みからも大きな刺激を受けたと話す。

「海で採取して、すぐに会社に戻って顕微鏡で覗かせてもらったのですが、すごく面白かったですね。平面でしか見ていなかったものを顕微鏡で立体として見ると、角度によってかたちも違うし、そのディテールを刺繍で出したいと強く思いました。色の見え方も写真と実物では異なり、やはり生きている珪藻はさまざまな表情を持っていました。これは大きな発見でした」。
さまざまな資料や素材、そして何よりも豊富な知見を提供してもらったが、いまはつくりたいもの、やりたいことが多すぎて、展覧会の開幕に間に合わせるためにどこからかたちにしていくかに悩まされているという。海も大気も川も地中も含め、あらゆるところに存在して、目に見えない存在でありながらじつは身近な珪藻をアートでどう可視化するか。「珪藻の存在を知らしめてほしい」という石井社長の思いも作品に込める。
3名のアーティストが考えるアート×サイエンス・テクノロジーの意義
──3名の話を伺うと、いずれも企業や研究機関とフラットな関係で、一方通行ではない協働が行われていると感じました。
川松 理研チームの市橋さんと対話をしていると、ものすごく柔軟なんですよ。科学の分野にいるからこういう見方をするべきだ、という思考がそもそもなくて、僕の考えについても抽象度が高い状態のまま読み込んでくださって、柔軟に理解して受け止めてくれる。そこにはすごく驚かされました。
宮田 SeedBankの石井社長も、アクティブでフットワークが軽いです。よくおっしゃっているのが、「無駄なことが好き」という言葉で、無駄と思われているところにアイディアや面白さが含まれているので、一見無駄なことでも向き合って、急がば回れじゃないですけど面白いことが生まれる。刺激的ですね。
三原 mui Labのエンジニアとデザイナーのチームとやりとりをしていますが、僕はシステム的な仕組みも含めてすごく興味があるので、あまり外注しないで、自作でプログラムから機械の制作など基本的には全部やりたいクチなんですね。muiの皆さんは、細かい技術仕様についても「これはできる」「解像度がどのくらいになる」「ビットレートはどのくらい」ということを明快に共有してくれるので、ここから何が立ち上がってくるのかを一緒に楽しみにしている感覚があります。
川松 結構ざっくばらんに教えてくれちゃうんですか。
三原 もちろん企業秘密の部分はあると思いますが、何ができるかできないかということを共有していないとプロダクションの効率に関わってくるので、具体的な質問をするとそこにはピシッと答えてくれますね。
──コラボレーションを通じて新たに得た刺激が、今後のご自身の制作にどうフィードバックされると考えますか。
川松 私はアイデンティティを一貫したテーマとして扱っていますが、いまは記憶を再編することでアイデンティティを分有できないかと考えています。これまでは人間としての尺度からしか記憶を考えていませんでしたが、そこに植物の尺度が加わりました。植物が記憶を持つとしたら、それは生態系の中に眠るのではないか。そうなると、植物の記憶というのは、土壌も水もあらゆる環境要素も含めて分有されているのではないか。そう考えることができます。
それは人にも置き換えられるはずです。記憶が本人に眠っているだけではなく、いろんなところに眠っている可能性があって、それを分有と考えてもいいのではないかと思えたことは新たな気づきです。そうすると、もっと大きくアイデンティティを定義し、考えることもできるはずなので、作品の文脈には変化が生まれると思います。
三原 僕はあまり作品の完成形を想像しないで制作をするんですね。何かやりたいことがあって、それにトライした結果、こういうことが起こったからこれが作品なんだ、となるみたいな。去年のNISSAN ART AWARD2020のときは、雲をつくりたいとか雨を降らせたい、ということをざっくり考えたことがスタートです。夏に冷たい飲み物を置いておくとグラスに結露しますが、それを人工的につくりだす装置で、展示空間に含まれている湿度を液化するインスタレーションをつくったんですね。
そういうふうに、「なんか面白そう」というふわっとしたアイディアから、とりあえずやってみないとわからないからやってみようと始めるわけです。mui Labさんは僕のそういうふわふわしたイメージに対して、技術的なフィードバックをピシッとくれるので、情報を伝える技術を使って、質感やニュアンスみたいなものを伝えられるアートの可能性をもっといろいろと実験したいと思っています。
宮田 私は刺繍のデータをコンピュータでプログラミングして、あえてバグを加えることで、本来縫えない縫い方をミシンにさせる方法をとっています。なぜそうするのかというと、誰が縫っても一定のクオリティに仕上がるものを私が作品に使う必要はあるのか、というのがひとつ。もうひとつは、本来とは違うやり方で無理矢理行った刺繍のディテールがすごく美しいんですね。
失敗であるはずのバグから美しいディテールが生まれるギャップに面白さがあるので、それが生物の突然変異や進化の過程の変容と重なります。珪藻の培養はとても難しくて、本当にトライアンドエラーの繰り返しです。未知なるものと向き合い、そこを追求することは自分もしてきたつもりですが、それは間違っていなかったのだとSeedBankさんから改めて教えていただけたのは大きな励みとなりました。
──アートとサイエンス・テクノロジーの協働には、大きな可能性があることが伝わってきました。
川松 知性を共有する可能性を感じられますし、企業や専門家の協力を得ることでそれを適切にアウトプットできる方法論を手に入れられることは、コラボレーションの魅力だと思っています。いまは正解を急いで出すことを求められたり、正しくあることを求められがちな時代ですが、本来協働って、正解に辿り着くことが目的ではないはずですよね。
三原 今回おもしろかったのは、僕がmuiLabで活動のプレゼンをしたときに「アーティストってこういうこともするんですね」と言われたことです。アーティストでもエンジニアでもデザイナーでも、個人対個人でやりとりすると、互いのイメージは漠然としたイメージから具体的なものに変わりますよね。企業とアーティストが商品づくりを目指してコラボレートすると、目的化されて余白がなくなってしまいますが、KYOTO STEAMでは整合性の取れた物語は求められていないので、アーティストも企業・研究機関もマインドセットが大きく変わるんじゃないかと感じます。
宮田 KYOTO STEAMのおもしろさはまさにそこで、冒険ができるコンペだと思います。逆に、いつもと同じ作品を出したら「それ違うでしょ」となってしまう。自分らしさを残しつつも新しい世界観を出したいというのが私もすごくあって、それを正々堂々と冒険できる機会はあまりないので、今後も長く続いて欲しいコンペだと思いますし、このコンペがきっかけで知り合った企業さんとも関係が続いていくことを願っています。




























