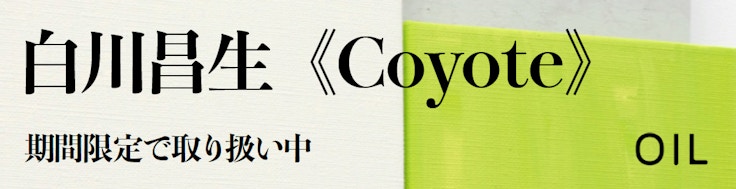マイナーから普遍に至る道のり
──白川さんはご自身の活動を「マイナー」という言葉で語られていますが、群馬という土地に結びつくプロジェクトを実施され、執筆活動も盛んないっぽうで、立体作品の制作も精力的に行っています。ご自身の活動において、立体作品をどのように位置づけられていますか?
立体の作品は、デュッセルドルフ国立美術大学で学んでいた1970年代からつくっていました。日本に戻ってきてからも、ドイツのときの活動の延長でやっています。とくに帰国後は、立体の形や色、空間を考えているときに、その由来が、自分が生活している場所なのか、自分が育った文化的な領域なのか、そういうことを考えるようになりました。
歴史や文化の問題を、造形と並行して考えなければいけないのです。自分が生活している群馬で、場所や、自分がこれまでに蓄積してきた過去の記憶、文化的なものを考えながら、制作を続けていければと思っています。
──70年代に渡欧され、81年に卒業したデュッセルドルフ国立美術大学では、ギュンター・ウッカーに師事しています。大学教育の課程では、色や形を主題として扱われていたのでしょうか?
デュッセルドルフ国立美術大学のカリキュラムには、日本のような絵画科や彫刻科はなく、フライエ・クンスト(自由美術)とされていました。ヨーゼフ・ボイスはもう教鞭をとっていませんでしたが、ウッカーのクラスもゲルハルト・リヒターのクラスも、フライエ・クンストが基本でした。
美術史や哲学の授業はありましたが、それよりもクラスにいるドイツ人や、ほかの地域から来ているアジアや東欧のアーティストたちといっしょに制作し、話し、作品を見ながら、自分で考えたことのほうが、制作への影響が大きかったですね。
ウッカーのクラスでは、地域に出てアートの活動をするということを当時から始めていました。芸術での地域おこしの成功例として日本でもよく取り上げられる、ツォルフェアアインという炭鉱町のプロジェクトにも、アカデミーが関わっていました。いまは日本でも地域おこしのための芸術祭がありますが、既に70年代からドイツのアカデミーでは行われていました。そういったドイツでの学びは、日本に帰ってきて活動を始めるときも、参考にしました。
──オルタナティヴ・スペースや留学制度の充実といった当時のドイツでの動きが、同時代のアメリカを中心とした、抽象表現主義やミニマルアートなどのマーケットを巻き込んだ権威に、対抗する力をもっていたと以前おっしゃられていました。
マーケットの問題も、僕がデュッセルドルフで学んでいるときに、大きな流れとして出てきました。ヨーロッパでも、ケルンやバーゼルなどのアートフェアで、アメリカのミニマルアートの作品や抽象絵画が出品されていましたが、作品のサイズが大きいんですよね(笑)。だから、高くて取引ができないような値段になってしまっていて、結局マーケットが動かない。
そういう状況から、アメリカと同様に、ニューペインティングの運動がイタリアやドイツでも起き、低価格で、作品のサイズも適度なものが、抽象表現主義とは違うかたちで受け入れられていきました。美術館もその流れに合流することで、2、3年くらいのあいだにマーケットが活性化し、アメリカの美術から離脱して、ヨーロッパの美術になっていったのです。マーケットをヨーロッパだけで回していけるよう、かなり意図的な操作が行われるのを見ていました。
──いっぽう、日本については、フォーマリズムを無批判に受容する態度を、83年に帰国された際に問題視されていらっしゃいましたね。
不思議だったのは、ドイツにいてもフランスにいても、たしかにフォーマリズムの考え方は共有されていたけれど、教条的にとらえている人は誰もいませんでした。いっぽう、当時の日本のアート界では、最初から数学の公式のようにフォーマリズムという普遍があると思っていて、それをみんなが扱おうとする状況でした。
例えばポール・セザンヌも、南仏に住んでいた時期は、かなり地域的なアートを制作していたといえますよね。現在におけるセザンヌを普遍的とするならば、その普遍性を獲得していった過程が重要になるはずですが、日本のアートの場合にはそれが見えませんでした。最初から普遍を追い求めてしまい、いずれ普遍に至るという考え方がなかったんです。

メルド(糞)彫刻とは何か
──当時の国内の状況を批判的にみつつ、群馬を拠点に活動されてきました。白川さんは、90年代に群馬の山奥で合板という素材を見つけられて以降、現在に至るまで素材として長く使用されています。
群馬の山の中には、捨てられた廃材がたくさんあります。東京でビルをつくったときに出たゴミを、処理業者が群馬までやってきて捨てていくわけです。東京でゴミになったものを、群馬で見つけて作品にし、東京に持っていきます(笑)。
廃材が捨てられるそんな群馬の山奥で生活している人が、僕もよく知るドイツの炭鉱で働いていたと言っていたことがありました。片田舎のものが、たまたま作品に使用した山奥の合板によって、ひとつのブーメランとして世界につながっていくという実感をもっています。
また、ヨーロッパでは既に、大型のホームセンターがアメリカと同じように存在していたわけですが、80年代の初めくらいの日本では、まだ出店され始めたばかりでした。そういうホームセンターで大量生産、大量消費される合板をはじめとする製品を、ぼくは材料として使っています。イタリアのアルテ・ポーヴェラ(貧しい芸術)と同じように、廃品、身近なもの、複製品を使って作品をつくるわけです。
──白川さんは廃材という捨てられたもの、つまり経済的な体系から脱落したものが、作品として再び商品価値をもつような循環の構造に興味をもたれています。それは00年代以降に実践されてきた「メルド彫刻」とも、関係性があるように思えます。
「メルド」はフランス語で「糞」ですよね。79年に練馬区の江古田にあったギャラリーメールドでボイスの資料展を開催したことがありました。そのときボイスから、東京の小さなオルタナティブギャラリーであるギャラリーメールドの名前について「メルドというのか?」と聞かれたので、「アートって『メルド(糞)』じゃないですか」と答えたら、ボイスも「そうだ」と言ってくれて(笑)。
ボイスもまた「シャイセ(糞)」というメルド的な作品もつくっています。表現というのは人間の体から出たものだから、そういうものが大地とつながって、生産的なものに変わっていく。そういう意味では、メルドという言葉はいいんじゃないかなと思っています。

──過去には、「メルド」をクルト・シュヴィッタースの構成的な作品「メルツ絵画」と関連させる発言もありますね。また、村山知義とシュヴィッタースの比較をされ、シュヴィッタースの作品を理知的であり、自宅の生活空間を人工的造型空間につくり変えたと分析されていました。
シュヴィッタースのまわりを取り巻いていたアート的な制度の成熟の問題もありますが、彼はすごくアヴァンギャルドないっぽうで、マーケットにも敏感で作品を売ったり買ったりしていました。僕は、シュヴィッタースみたいな制作はできないと思っていますが、彼が生活の中でつくり続けたことには共感できます。あれほど大きなスケールでは難しいですが、自分のつくる彫刻が、常に彫刻として可能かどうか、その可能性を探ってみてもいいのかもしれないと、いろいろ試しています。
──「メルド彫刻」においては、DIY(=Do It Yourself)もキーワードとなっています。
廃材はもちろん、ホームセンターにある素材や、身の回りの題材を使って、基本的に全部ひとりでアートを制作するのがメルド彫刻です。
例えば、今回の個展「夏の光」で展示している《弁天通り商店街の光》(2014)は、地方の田舎の、どこにでもあるシャッター商店街のアーケードがある空間から、アートがつくれるかという問題意識でつくりました。セザンヌがサント・ヴィクトワール山を描いたように、普遍を目指すような糸口が、シャッター商店街にあるかもしれないと思っています。

──人間から出た残余が、生産的なものに変換されるという、循環性の問題も重要だと思われます。廃材を使用することで、群馬と東京で作品が循環するという先ほどのお話とも関わりますが、白川さんは「円環」という言葉でそれを語っていらっしゃいます。白川さんの造形の特徴に円がありますが、それは幾何学的な円ではなく、そういった循環性という意味までを込めて選ばれているのでしょうか?
そういうことを考えていますね。昔、『サークル』(1979、ギャラリーアウラ ブッポタル)という本をつくりました。円の形と円が示す始まりがあって終りがあるという思考のパターンや、現実にある日常の中のかたちを1冊の本にしたのです。形や思考、現実のフォルムを行ったり来たりしながら、考えるということをいまも続けています。
──過去には、「凡庸な日本人」として円を考えてみるというご発言があり、円を造形に援用することを、実験ととらえていらっしゃいました。日本における円というと、仙厓の《円相図》や吉原治良の作品など、美術にも数多くの参照項があります。
日本的な円については考えられるなと思いますが、ひょっとすると、ほかの国や地域にもあるかもしれません。円のシリーズで、第二次世界大戦のときに、日本の空母赤城が沈められるところをアメリカ軍が上空から撮影した写真をモチーフとした作品があります。回りながら逃げた航跡が、ちょうど円の形になり、最後は沈んでしまう。
仙厓においては、意味としては非常に象徴的な方向にいきますが、現実はすごく複雑です。自分の身のまわりを見ても円はたくさんあり、それらがすべて共通性をもっているかなんて誰にもわかりません。でも、やはり人間のなかに円はあるし、使ってしまう。それがなぜなのか、たくさんのデータを出してきて、眺めて、考えてみています。
──1983年には「日本のダダ─日本の前衛 1920−1970」という展覧会を、ドイツのデュッセルドルフ市立美術館で企画されています。その企画意図のひとつとして、なぜ日本の前衛運動は円環的、つまり反復をしているのかという問題を提起されました。そのような悪循環をくぐり抜けることでしか、新しい表現は生まれないという考えが白川さんにはあります。安易な象徴形式としての円におちいることなく、変わり続けていく運動体としての円環が、作品のフォルムにも現れているのですね。
そうですね。「日本のダダ─日本の前衛 1920−1970」では、絵画と彫刻を意図的に取り上げず、演劇やパフォーマンスに絞り、身体的な感覚や身体が感じる文化的なもの、それらがいったいなんなのかというのを考えてみましたが、なかなかわかりませんでした。
ただ、現象として考えてみると、たしかにアジアでは、それが突出したかたちで現れたのだとは言えると思います。細かく調べればヨーロッパにもあったかもしれませんが、ヨーロッパだと、やはり哲学などの概念的な操作や歴史があり、自分がやっていることをきちんと概念化し、論理化、歴史化します。アジアではまだそこまでしっかり検証できておらず、まずは体でやってみて出てきたものがなんなのか、いろいろ考えている状態じゃないのかなと思っています。
──身体感覚についてですが、2017年のMaki Fine Artsでの個展「Coyote」では《Coyote》シリーズが発表されました。74年にボイスが行った、コヨーテと過ごすアクションからの影響も想起させますが、白川さんのステートメントを読むと、動物の身体性や知覚の問題から作品が生み出されたことがわかります。今回の個展の作品を見る際にも、60年代のアンソニー・カロの彫刻や、ロバート・モリスの「アンチ・フォーム」と呼ばれる柔らかな素材による造形を参照点にしてしまいがちです。しかし本当は、かつてのアメリカの芸術における、いち動向のシミュレーションとしてではなく、見過ごされがちな細かな差異にこそ目を向ける必要があるように思われます。
彫刻を構成する際に、それぞれのものがつながる身体感覚が、見る人にも伝わればいいなと思っています。僕の作品は、それほど目新しいものじゃないから「既に知っているものだ」と評されることもある(笑)。それはわかるのですが、もう少し微妙なところもできれば見てもらいたくて、とくに空間にまつわる身体的な部分を見てもらえばと思います。そういうところに、もしかすると日本で彫刻をやる可能性があるのかな、と考えています。

(c)Maki Fine Arts
形を与えることの意味と意義
──「夏の光」からは、合板の微妙なカーブや、接合された部分同士の接合に、身体性が読み取れます。また、ギャラリーの白い空間におけるレモンイエローの色彩が目を引きました。かつて「引込線 2015」で展示された《首のない馬》(2015)でも、馬に塗られた青は会場壁面のタイル、排泄物である尿の不定形な造形は床の緑と、空間との対応関係が見られました。
《夏の光》で使用しているレモンイエローは、僕がつくったものじゃなくて、ホームセンターで缶に入って売っているできあいの色です。《弁天通り商店街の光》の布も、溶剤で溶かして染色しただけなので、そのままの色です。あまり手を加えないDIY(笑)。そういう素材でつくれるアートの可能性もあっていいかなと思っています。

──先ほど触れたカロの作品は、工業用塗料が塗られて原色に近い色彩です。いっぽう、白川さんの作品は、空間と断絶しないような中間的な色を、意識的に選ばれているように思えます。
カロなどの場合は、ある種の原理的な部分を考えて、おそらく色彩表などを見ながらきちんと選んでいるのでしょう。僕が作品に使っている色は、ホームセンターで売っていて、普通の人が生活するのに違和感がない、毎日が快適にすごせるというインテリアのための色です。ほかにも、ちょっとした薄い青やピンクといった色のあるシリーズで、そういう凡庸な色が、僕はいいんじゃないかなと思っています。原理原則というマッチョなものを目指しているわけではないんです。
また、この色は、消費社会の中で、多くの消費者にとって生活するうえで良いとされる色です。この色が良いという企業側の提案でもありますね。そのような色を使って彫刻をつくれる可能性があるわけです。これも、メルツまではいかないまでも、メルドなのかな、と思っています。
──「夏の光」という展覧会のタイトルからも、今回の作品は、光がテーマになっていることがわかります。モチーフとされる商店街の窓やアーケードは、まさに光の通路であり、知覚に直接訴えかけるものです。そういった立体的な空間が平面化され、さらに布による立体へと落とし込まれていますね。
黄色を使うと物質感が軽減されますし、黄色自体は透過性がすごく高いので、強さがなくなっていくんですよね。それは人が光を見て感じる感覚に近い。物質的な窓というか、形というか、そこに光があたっている感覚です。それをとらえて今度は形にしてみるといった感じです。

──商店街の店舗のガラスの窓の形を布に変換されているのは、前橋が過去に繊維街であったことと関係がありますか?
ありますね。今回展示されている作品は普通の綿を使っていますが、以前には絹を作品に使ったりしました。いま僕は服飾専門学校で働いているので、僕が型紙をつくって学生にミシンで縫ってもらいました。染色も学生にお願いしています。
──《夏の光》とともに展示されている《弁天通り商店街の光》の布は、写真という過去を記録するメディアと組み合わされています。これは、展覧会名の「夏の光」を「“あの”夏の光」と言い換えるような、記憶を呼び覚ます要素を含んでいるのではないでしょうか。メルド彫刻と並行して、白川さんが強い関心をもたれている記憶やモニュメントの問題は、本作と無関係ではありえないと感じました。
モニュメントは公的なものだと思われがちですが、むしろ個人的な領域の記憶に関わるものです。個人的な記憶を作品として出すことで、ほかの人がそれを共有できる。アートとはそういうものではないでしょうか。このように発表することで、ほかの人が目に見えないものが見えたり、触れたりして、知覚できるものになる。個人的な感覚や知覚、記憶みたいなものをとにかく形にして見せている。それには終わりがないんですよね。絶対これという形がないわけですから。
──モニュメントの問題としては、群馬県立近代美術館の「群馬の美術2017」で出品が取りやめとなり、あいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展」に出品されることになった《群馬県朝鮮人強制連行追悼碑》(2015)も思い起こさせます。
モニュメントはひとつの共同体であり、地域の共有できる記憶です。人間は日常の中で常に他のこともしなければいけないので、記憶は何かのきっかけがないと呼び起こされないわけです。呼び起こすための装置として、モニュメントがあると思うんです。モニュメントがなくなると、共同体なり、共有できる記憶がなくなるわけですよ。存在していても、誰もそれを呼び起こせない。
特に日本の彫刻を考えたときに、戦争に関する彫刻は、見る人の問題もあるけれど、つくる側の問題もある。日本人の彫刻家は、つくり、残っていくものとして、これは本当にいいのか、共有すべき記憶なのかということについて、これまであまり考えてこなかったと思います。

──今回のインタビューを通して、白川さんのご活動からは、異なる価値観を緩やかな緊張状態におき、それらが可変的に組み替えられる通路をつくるような可能性を感じました。とくにモニュメントでは、人間の記憶の喪失や変質に、物質がどのように与することができるのかが追及されています。多様なご活動をボイスに還元すべきではないことは承知していますが、白川さんが書かれたボイス論では、キリスト教的な「霊の物質化」、つまり錬金術的な造形にこそ、ボイスの本質があるとおっしゃっていたことが思い出されます。加速主義をはじめ、資本主義の閉塞的な状態を脱しようとする考え方が現代思想の文脈で展開される、切迫した時代背景からも、長年の白川さんの実践はいま注目されるべきだと思います。
そういった感覚や概念を、哲学者は言語にしますが、ボイスは形にしているということです。造形というとおかしいかもしれませんが、言語の並べ方や定義で、理論を考える。そういう感覚がヨーロッパの人たちにはあると思うんですよね。
やはり夢かもしれませんが、資本主義を乗り越える可能性を本気で考えないと、かなり厳しい。いろいろなところで問題が起こってしまうと思うんです。マルクス主義でもジル・ドゥルーズでも十分ではないし、やはり難問だと思います。でも、本当にそれを可能にしていく糸口を考えなければいけない。その問題は、アートの問題とつながっていると思うんです。