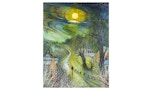展示室1
まず鑑賞者を迎え入れるのは、色とりどりのガラス製の鶏の足でできたカーテン《Money Grab Hand》(2024)である。世界各地には鳥を用いた占いである鳥占術が存在するが、その形状が「お金を掴む」動きに見えることから、中国各地で幸運の象徴とされているという。鳥の足が天井から無数に吊るされた本作は、その先に広がる展示空間を魔術的な舞台装置へと転換する結界として存在すると同時に、カラフルでポップなそれらは生死のサイクルを演劇的な機能へと還元し、不気味かつシニカルに現実の足場を揺るがせる。

Commissioned by Tai Kwun Contemporary
カーテンの先に進むと、空間を縁取るように砂漠が現れる。干からびた草が少しだけ生える不毛な砂漠に置かれるのは、石化した蛇が陶製の便器に巻きついていまにも割れそうになっている彫刻作品《Cuddle》(2024)である。そこでは、巻きつく圧力があと少しでも強まれば割れてしまうであろう緊張感と、石と陶器という素材であるがゆえにとどめられた一瞬の永遠性が同居している。様々な伝説や神話に登場する蛇と、私たちの世俗的な生活と結びついたトイレという2つのモチーフ。現実と虚構、破壊と創造。そのどちらかに属するのではなく、両者が生み出す絶妙な緊張感のなかに鑑賞者が置かれる。また、砂漠はデジタルを思わせるようにカクカクとしており、仮想的な空間へと転換されている。

Commissioned by Tai Kwun Contemporary
そこに対置されるのが、映像インスタレーション作品《Chilling Terror Sweeps the North》(2024)である。同作では、中国北部の乾燥した山岳地帯出身の女性と、愛を求める中国南部出身の男性をめぐる物語が描かれる。彼女との愛のために生きることを願う男性は、北部の過酷な気候のなかで生きる彼女を都会的な南部へと連れ出そうと説得を試みる。しかし、自らが生まれ育った厳しい環境のもとで生きることを望む彼女は、最後まで彼を真に受け入れることができない。彼女が劇中で語る「When you live in cruelty, you are forced to use cruelty as a tool(残酷さの中に生きるとき、残酷さを道具として使わざるをえない)」というセリフは、自らが置かれた環境を客体化することで道具化し、それをもって残酷さに対峙するというひとつの可能性を提示する。しかし、彼女は自身に対しての葛藤や現実の残酷さに苦しんだ末に自らの頭部に当てた銃を引く。

悲しい物語ではあるが、映像自体からインスタレーション全体へと意識を向けると、それがまた虚構であることに安堵する。傍らで胡琴を奏でるホログラムの奏者が、スクリーンの中の物語の戯画性を強調するかのように儚くその姿を消していく。伝統的な中国の寺院の外観を模した構造物は、金属の骨組みやそれを囲うプラスチックのパネル、ビニールでできた大理石調の床など、仮構性が強調される。悠久の時間を想起させる寺院建築と素材が持つ一時性。ここでも両極の二択が生み出す緊張感が、舞台装置としての虚構性を際立たせる。これらの外縁を囲むデジタルな質感を伴った砂漠のセットは、映像内外の世界をリンクさせる。それにより鑑賞者は、自身が置かれた空間が現実と虚構がねじれた場であることを意識する。

Commissioned by Tai Kwun Contemporary
このようなドラマ・映画的な虚構性には、陶の制作を裏付ける幼少期の体験がある。山岳部の田舎村で生まれ育った彼にとって、テレビで放映されるソープオペラは、単調な毎日という冷たい現実に唯一希望の光を差し込むものであった(*1)。ここで示される物語性に依拠した虚構性は、次の展示室でより個々人の日々の生活に根差したそれへと位相を移す。