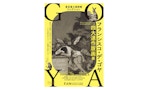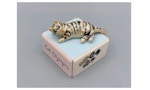哲学的な問いを投げかけるモノトーンな作品世界
インドのムンバイ出身で現在はロンドン在住の、現代美術界を代表するアーティスト、アニッシュ・カプーア。近年では、2012年に構造デザイナーのセシル・バルモンドとロンドンオリンピックの記念モニュメントの設計を担当し、15年にはヴェルサイユ宮殿で個展を開催するなど、常に国際的な注目を集めている。
「この展覧会では、空っぽな物体/対象(オブジェクト)の制作を試みています。しかしながら、それはたんに空っぽであるというわけではありません。そこには常に『空虚が満ちているのか?』という両義的な問いかけがあります。どのようにしたらそれが可能になるのか、それはいったいなんなのか──それは物体/対象と、そのリアリティーの本質、あるいは物質(マテリアル)/非物質(ノンマテリアル)についての根源的な問いです。この20年間、人類はとりわけ物理学の分野において、この物質性(マテリアリティー)の始まりについて多くの努力と発見を重ねてきました。ここでより重要なことは、私が作品制作を通して追い求める物質とは、たんなる物理的な物質ではなく、より普遍的な物質であるということです」。

ギャラリーに入ると、手前の部屋の中央には透明なアクリルを用いた立体作品、壁にはカプーアのトレードマークとも言えるステンレスやファイバーグラスを用いた皿(ディッシュ)シリーズの新作が展示されている。また、奥の部屋にも同シリーズの新作と、和紙にガッシュで描かれた抽象画、そして中央のテーブルには建築模型が数点展示されている。
「アクリル・ブロックの内側にもうひとつのアクリル・ブロックが入れ子状に入った新作《無題》は、一見しただけでは中に入っているブロックがあまりよく見えません。不可視の物体/対象です。私はいつも知覚の小さな変化に興味を持っていますが、それはまさに最高の遊び(スーパー・プレイ)です。いつ見ても同じように見える作品とは異なり、見るたびに何か特別な体験をもたらしてくれます」。

カプーアの作品を特徴づける要素として深淵な「暗闇」の存在がある。それは物理的な体験であると同時に心理的な体験でもある。彼は2014年に英国の企業サリー・ナノシステムが開発した、史上もっとも黒い物質「ベンタブラック」を作品制作に取り入れている。この素材は、カーボン・ナノ・チューブを用いることで、可視光の最大99・96 パーセントを吸収するという。
「テーブル上に展示している建築模型は、ベンタブラックを使うことを想定しています。それは真っ黒で、物質というよりはまるでブラックホールです。それ自体がひとつの物語、あるいは驚くべき物質の神話を体現しているようでもあります。開発当初は、2センチ四方程度の大きさしかつくることができませんでしたが、近い将来、私たちの身体や知覚空間を包み込むことができるくらいの大きさの作品もつくれるようになるでしょう」。


テーブルに載る小さな作品から屋外に設置する巨大なインスタレーションに至るまで、カプーアの作品群が持つ独特なスケール感とミステリアスな体験を支えるのは、人間の知覚空間における微小な揺らぎに迫る最先端の科学技術だけでなく、素材それ自体が持つ原初的な普遍性である。
「新しいアートをつくるためには、エモーショナルな空間をつくり出す必要があります。それは異なるイメージやかたちのことを指しているのではありません。スタジオで何かをつくったときに、その物体/対象をしっかりと観察し、考察しなければなりません。これはいったいなんなのか、なぜそれなのか。そこには複雑な物語が存在します。制作プロセスや技術的な問題は後で考えればいいのです。物体/対象との間で意味のある会話が必要なのです」。
現代社会に向き合うアーティスト
2013年には東日本大震災の被災地支援プロジェクト「アーク・ノヴァ」で、バルーン型移動式コンサートホールを磯崎新と設計し、また、15年には艾未未(アイ・ウェイウェイ)とともに現在欧州で起こっている難民問題に抗議するためのパレードを行うなど、社会的な活動にも精力的に取組んでいる。
「アーティストにかぎらず、作家、詩人、俳優、ミュージシャンなど、芸術文化で活動する人々が政治について考え、人類への問いかけとして声をあげることはとても重要なことです。いま何をすべきか、そして何をすべきでないか。いま世界には6000万人以上の難民が世界中をわたり歩いているといわれています。21世紀に入ってもなお、なぜお金が人の生命よりも重要とされているのか。とても重要な問いかけです」。

以前、カプーアはインタビュー(『美術手帖』1999年7月号)において、自身のことを「間にいる人(Mr. Inbetween)」と称し、かつて現代美術の巨匠たちが実践した、「物質がすべて」(ドナルド・ジャッド)と「物質はもっと複雑で大きな物語の記号」(ヨーゼフ・ボイス)の間──抽象と象徴の間で制作をしていると語った。現実と非現実、内と外、2Dと3D、見えるものと見えないもの......。途方もなく両極に離れたものの「間」が、やがて微小な差異しか持たない、限りなく透明に近い境界としての「閾(いき)」に変容する。彼はそのような世界を私たちに提示しているのかもしれない。
(『美術手帖』2016年12月号「ARTIST PICK UP」より)