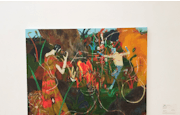深い森のアンビエンスで見る「ひとつの景色」
本展は、2015年に25歳で夭折した中園孔二の平面作品を48点集めた美術館における初の個展である。本展タイトルは、一つひとつの絵画の「内側」に何が描かれているかではなく、複数の作品群によってそこにある見えない景色の「外縁」をつくること、という中園の言葉を引用して付けられている。
中園は主に油絵というオーソドックスな手法を尊重しながらも、そこから自由に飛び出すかのように、しばしば即興的に指やティッシュなどを用いて、具象/抽象といった境界を曖昧にしていく。作品の表面においては、ユーモラスでありながらどことなくディストピア的な印象をも与える人型のキャラクター、多数の線の中に幽霊のように浮遊する顔といったイメージが、何層にも重ねられながら、鑑賞者の動きにあわせて大量に出現しては、変容し、消えていく。


筆者は、昨年の第7回モスクワ国際現代美術ビエンナーレにて、アシスタント・キュレーターとして中園の作品選出と展示のプロセスに関わったが、これほど多くの作品を同一空間で鑑賞するのは初めてのことであった。多作で知られる中園の作品を一挙に展示する本展を通して、彼の述べる「外縁」について、限られた字数の中で記述することの困難に再度気付かされる。
例えば、個別の作品の表面を記述しようとすれば、大量に生成されながら変容する多重人格的なイメージの体験を取り逃してしまう。また、作品同士によって展示全体に生まれる物語をとらえようとすれば、個別の作品の表面にある塗り残し、かすかにつけられた表面のスクラッチの線、固着する油絵具のマチエールといった、イメージ生成のもととなる中園の固有の断片が捨象されてしまうことになる。展示空間を歩いていると、こちらを見つめては消えていく顔に誘われるようにして、彼がしばしば夜中に出かけていった森の深層に迷い込んでいくような感覚に包まれていく。

モチーフやそれが描かれた手順、あるいは作品に共通して見い出せる「不安」という心理的状態といった一つひとつの要素に焦点を当てて分析しようとすれば、別の層に潜在している物語のなかの幽霊的なイメージたちは、まさに作品に描かれるピエロのような顔が見せる「泣き笑い」の表情で、逃げ出してしまうかのようである。
つまり、中園の「見てみたかった景色」とは、おそらく分析(analysis)からも統合(synthesis)からも抜け出ていってしまう何かだ。そして、そうした掴みどころのない景色に少しでも歩み寄るためか、本展でも単純な並列ではなく、大小の複数の作品を壁一面に散らしながら構成するなど、作品のインスタレーションに工夫も見受けられる。そこには、作家亡きいま、どのように彼の言う曖昧な「外縁」を編んでいくのか、というキュレトリアルの葛藤もあるだろう。

中園は短い生涯のなかで数多くの作品を残している。しかし、夥しい数のイメージをまさに「壊れた機械」(*1)のように即興的に生み出し、それらの直列と並列を繰り返しておきながら、端的なイメージの氾濫を起こすわけでもなく、統合性や全体性をつくり出すわけでもない。
中園は、ひとつの原初的でリアルな身体を持って、Google画像検索のように環境のありとあらゆる水平的なイメージや情報を取り込むと同時に生成し、複層的な物語を描き出していったのだろう。そのなかには、自然災害を喚起させる枝葉のない木々や、ネットワークに埋没していく身体が含まれている。私たちにはもはやブラックボックスとなったAIのディープラーニングにも似た速度、プロセスの見えない高速のアルゴリズムのように、イメージは瞬く間に生み出され、重ねられていくのだ。
そして、そうした「不安」を呼び起こす、暴力的とさえ形容できるイメージの生成速度が、他方で逆説的につくり出すのは、特定の記述や記録から逃れうる、「批評」や「肯定」もなく(*2)「どっちつかずでなんでもない」(*3)がゆえに、どこか持続可能で穏やかなアンビエンスである。そうした破壊的な制作量と児童絵本のような和やかさの強い対比によって、鑑賞者の知覚はときに通常よりも圧縮され、ときに暴発的に過敏になることで、それぞれの主観的なイメージ体験は大きく異なっているだろう。

森の暗闇の中で不安に懐中電灯を動かせば、見える景色はその都度変容するが、見えない森のざわめきは確かに感じ取ることができる。それと同じように、中園孔二の作品が生み出す現代的な深い森のアンビエンスによって、鑑賞者の身体は、デジタルイメージに代表される現行のフラットな視覚世界においてはとらえがたい、持続するリアルな眺め(sight)=場(site)としてのサイトという「ひとつの景色」を、知覚することができるのである。

*1——中園の指導者であったアーティストO Junによる追悼文(『美術手帖』2015年11月号)の言葉を参照。本文はウェブ版美術手帖で閲覧可能。
*2——中園の同世代の友人であるナイル・ケティングは、埼玉県立近代美術館「NEW VISION SAITAMA 5 迫りだす身体」展(2016)のカタログに寄せたテキスト「マクドナルド、星、迷路」において、2人はパソコンで見つけたコンテンツを特に批評したり肯定したりするわけでもなく、ただ風景を眺めるのと同じように面白がっていた、と中園との思い出を振り返っている。
*3——中園は本展に出品されているインタビュー映像において、いちばん好きな色を「緑」と述べ、その理由を「一番どっちつかず」「中間にある」「なんでもない」色であるからとしている。緑色は中園の絵画において多く用いられ、作品の生み出すアンビエンスのひとつの要因となっている。インタビューはYouTubeで閲覧可能。