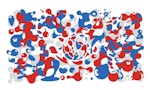──現在、山本現代での個展「ホイッスラー」と、森美術館(東京・六本木)で開催中の「六本木クロッシング2016展:僕の身体、あなたの声」において、連動するテーマで作品を展示されています。まずは、この2つの展覧会について聞かせてください。

2つの展示の共通のキーワードは「エネルギー」です。普段からさまざまな場面で目にする言葉ですが、まつわるイメージは人間の解釈や想像によってつくられたもののように思えます。それから、私たちがサプリメントや栄養ドリンクでチャージしようとする「エネルギー」と、電気や資源にまつわる「エネルギー問題」の「エネルギー」は、似ているようで違う。なじみ深い言葉ですが、実はとても曖昧な概念なんです。そういった疑問をきっかけに、特定のイデオロギーやその賛否を主張するのではなく、「エネルギーとはどういったものなのか」「どう私たちと関わっているのか」という問題について、考える契機となるような展示を目指しました。
ここでの私の最終的なクエスチョンは、地球や環境と人間との関係性。例えば、かつて原子力発電所の事故が起こったチェルノブイリはいま、放射性環境耐性のある植物や生物が生息する、とても美しい場所になっています。私の活動の根底には、「そもそも私たちはどこにいるべき存在なのか」「地球は私たちに適応しているのか」という疑問があるんです。
山本現代で開催されている「ホイッスラー」展の軸となっているのは、1920〜30年代の科学者、ヘンリー・モレー(Henry Moray 1892-1974)のストーリーです。モレーは「フリーエナジー」の思想に影響を受け、宇宙空間に漂うエネルギーを電気に変換し、集めるための機械「モレーコンバーター」を発明した人。電気を無償にするというアイデアを持っていたために、政治的な理由で身を隠していたし、機械は最終的になぜか共同開発者によって破壊されてしまい、その仕組みは謎に包まれている。彼のストーリーは、科学だけでなく、ファンタジーや政治など、多くの要素を含みます。

「ホイッスラー」展では、モレーにまつわる資料から発想した作品群を軸に、バイオエネルギーと関わりをもつコーンなどのオブジェクト、液晶画面に使われるリキッドクリスタルを用いた作品などが配置されています。そして、それらすべてのスカルプチャーをつなぐのが、会場内に流れる地球の超低周波。この展示空間自体が、「地球のエネルギーを聞く部屋」でもあるんです。
災害や不安定な世界の情勢のなかで、以前に比べて多くのアーティストやクリエーター、メディアがダイレクトに政治的なメッセージを表現するようになってきていると感じます。しかし、そういった活動は、表面的なパフォーマンスで終わってしまう危険性もある。そのなかで私は、問題自体にダイブし、そのなかで「プレイ」する手段を探したいと思っています。
──森美術館で展示されているインスタレーション《マグニチュード》でも、19世紀末の科学者であるエジソンなどがモチーフとなっています。人間の知覚や現代社会のさまざまな要素に言及しつつ、過去のもの・歴史的なものに注目しているのはなぜなのでしょうか。

撮影=永禮賢 写真提供=森美術館
電気をはじめ、新しい技術やものが発明されて間もない時期には、未知のものと人間との関わり方を探っている状態があります。そこに、私が関心を持っている、マテリアリティ(物質性)の問題をひもとくヒントが隠されている気がして。
さらに過去のものは、アーカイブされているという点で共有可能なものです。そういった意味で客観的なオブジェクトとして扱うことができるし、私たちがそれと呼応して、違う環境を生み出す手段になり得るはずです。軽快な見方で自由に歴史を扱うことで、現在や未来の社会環境との関係性を見出すことができると思っています。
──人間の知覚では感知できないものを作品としてビジュアル化しているのも、ナイルさんの作品に特徴的な点のように思います。
ずっと、私がいま生きている「現実」と、自分の「リアリティ」は違うと感じてきました。知覚できないものや不確かな存在のものをかたちづけていくことで、誰も定義していない新たなリアリティを生み出し、他の人と共有できるのではないかという気持ちがあります。
このような方向性は、2012年にベルリンに移住し、バックグラウンドを含め「自分」について考えるなかで生まれてきたものです。自分が抱えているのは、ジェンダーや身体といった要素ではなく、「私」という「モノ」に対しての疑問なのではないかと思い至った頃、イタリアの哲学者マリオ・ペルニオーラの『無機的なもののセックス・アピール』(平凡社)に書かれていた、「人間を感覚するモノとしてとらえる」という考え方にすごく共感して。自分が感じ取っていたことが、西洋哲学の世界で理論として成立していることに感動しました。それから、もしかしたら見えない存在をモノとしてとらえるためのアプローチが、リアリティを再構築する手段になるのかもしれないと考えるようになったんです。

撮影=永禮賢 写真提供=森美術館
──現在はベルリンに在住されているというお話がありましたが、1989年に鎌倉で生まれ、逗子で育ったそうですね。どういった子ども時代を過ごされ、どのようにしてアートの道に進んだのでしょうか。
本当に大変な子どもでしたね......。いわゆるハイパーアクティブの傾向があり、学校では問題児。いま考えると、自分の中に制御しきれないエネルギーがあって、それとどう関わっていけばいいのかがわからなかったんだと思います。親も私に何をさせたらいいのか思い悩んだようで、いろいろな習い事をさせてくれたのですが、結局全部ダメ。私にとって、子ども時代は暗〜いものだし、記憶もあまりないんです。先が見えないジャングルの中で迷っているような感覚でした。
アートに興味を持ったのは、小学校6年生のとき。たまたま親と一緒に「横浜トリエンナーレ2001」を見に行って「あ、こういう世界があって、こういうことをしてもいいんだ」と、動物的な感覚で直感しました。それから、「アート」を知るためにたくさんの展覧会に足を運びました。
そうして、多摩美術大学に進学したのですが、周りに美術館や舞台にあまり興味のない人が多く、同級生や先生と話が合わなくて。学校が楽しいと思えず、あまり行かなくなってしまったんです。そんな私を見かねて、当時、多摩美の助手だった秋山さやかさんが勧めてくれた、フィンランドのアールト大学に留学したのが転機となりました。
フィンランドでは、大学と同時期にシベリウス音楽院の音楽テクノロジー学部にも通い、サウンド・アートを勉強しました。そこが本当に面白いところで。ただでさえ人口が少ないまちで、サウンド・アートを学ぶ人なんて本当に少なくて、生徒は私を含めて3人。いちばん最初の授業は、1時間窓を全開にしてみんなで外の音を聞き続け、どう思ったかを話し合うというものでした。私は、解を与えたり、答えを探すのではなく、体感すること、迷うこと、発見すること、そのときのリアリティで判断することを大事にして制作していますが、そういった部分には、シベリウス音楽院での経験が反映されているように思いますね。
──サウンド・アートのほか、パフォーマンス作品も手がけられています。自分の身体を使ってパフォーマンスを行うことについては、どのように考えられているのでしょうか。

Photo: Catalina Fernandez / Eva Pedroza Courtesy of YAMAMOTO GENDAI
パフォーマンスを始めたのは2011年、ドイツ旅行中にたまたま参加したコンスタンツァ・マクラス & ドーキー・パークのワークショップで、ダンサーとして誘ってもらったのがきっかけです。偶然の巡り合わせだったのですが、ダンスやパフォーマンスを始めてみたら、本当にいろいろな発見がありました。
ステージ上で動いていると、自分が「アライブ!」と感じる瞬間があるし、疲れたときには水や食べ物を欲するというように、身体はものすごく高度にプログラムされていることも実感する。さらに、自分が「生きている」と感じる瞬間って、演出家からの指示など、何かしらそう感覚するための道筋が引かれているんです。それに気付いたときに、身体ってなんて人工的で、なんて自然なものなんだろうと気づきました。
そこからおのずと、こういった感覚をかたちにするにはどういう方法があるのか考えるようになりました。インスタレーションは自分たちと異なる存在としての「無機的なもの」に肉付けする作品が中心だったので、パフォーマンスでは逆に、私たちが肉付けされていると思っているものをモノ化するような作品をつくり始めました。ある意味、ペルニオーラの「身体とモノを水平にとらえる」という考え方にも通じますよね。ひとつのシーンや世界、生態系にアプローチするために、身体を装置・オペレーターとして扱う。私のパフォーマンス作品は、「モノ」なんです。
──最後に、今後扱っていきたいテーマについて聞かせてください。
いま興味があるテーマは、今回の個展で使っているUVプロテクトの素材やヘルメットなどのオブジェクトから派生した、「防御」や「防衛」の概念です。ミシェル・セールの『世界戦争』(法政大学出版局)を読み、「人類と世界の戦争」における防御やシェルターとは、どういったかたちをとるのだろうかと考えていました。同時に、タコとかイカ、カメレオンのように「自分を環境に同化するよう変化させて隠れる」という防御もありますよね。世界に溶け込んで「私」が見えなくなることは、人間にとっても防御でありうるのか......。こういった様々な切り口で、「防御」の概念とマテリアリティやパフォーマティビティにアプローチしたいと考えたりしています。

それから、「資本主義」もずっと関心を持っているテーマのひとつです。作品の制作のきっかけとなる要素はスタジオよりもむしろ、消費社会の現場や株式市場、研究所などにたくさんあるように思います。例えば、美容のためのビタミン剤、感覚や神経に働きかけるリラクゼーションオイルなど、身体に直接的に作用するものが経済システムのなかで商品として扱われていることに、とても興味をひかれます。だから、テレビ番組よりもコマーシャルやテレフォンショッピング、映画よりも予告編が好きなんです(笑)。
私は、アートワールドの中で特定の立場をとるものではなくて、世界の中で自足できる何かをつくりたいと思っています。作品そのものがエコロジーを持っていて、自分で生きていられる作品をつくりたい。手法や方法論は、「fail(失敗)」して自分ができないことを確認するためにある、発見の手段だととらえています。目指すのは、人に向けてつくるものや人の手に渡るものというよりも、外界に対して何かを伝えたり、つながることができる作品。そういうものは、最終的には人間にもきちんと届くと思うんです。近代以前には、届ける対象は神様だった。宗教が科学に置き換わった現代に、科学を題材としているのは、そういうことなのかもしれないですね。

PROFILE
ナイル・ケティング 1989年神奈川県出身。2012年多摩美術大学卒業。在学中にフィンランドのアールト大学に留学し、メディア、サウンドアート、 パフォーマンスを学ぶ。主な個展に「Hard In Organics」(山本現代、2015)、アートフェア東京での「ESSE」(東京国際フォーラム、2014)など。パフォーマンス作品やキュレーションも手掛けるほか、コンスタンツァ・マクラス&ドーキー・パークなどのダンス、シアターカンパニーにパフォーマーとして参加。ZKM(ドイツ)で開催中の「GLOBAL-New Sensorium: Exiting from Failures of Modernization」にも出品している。現在はベルリンを拠点に活動。