有識者が選ぶ2023年の展覧会ベスト3:中島水緒(美術批評家)
数多く開催された2023年の展覧会のなかから、有識者にそれぞれもっとも印象に残った、あるいは重要だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は美術批評家・中島水緒のテキストをお届けする。
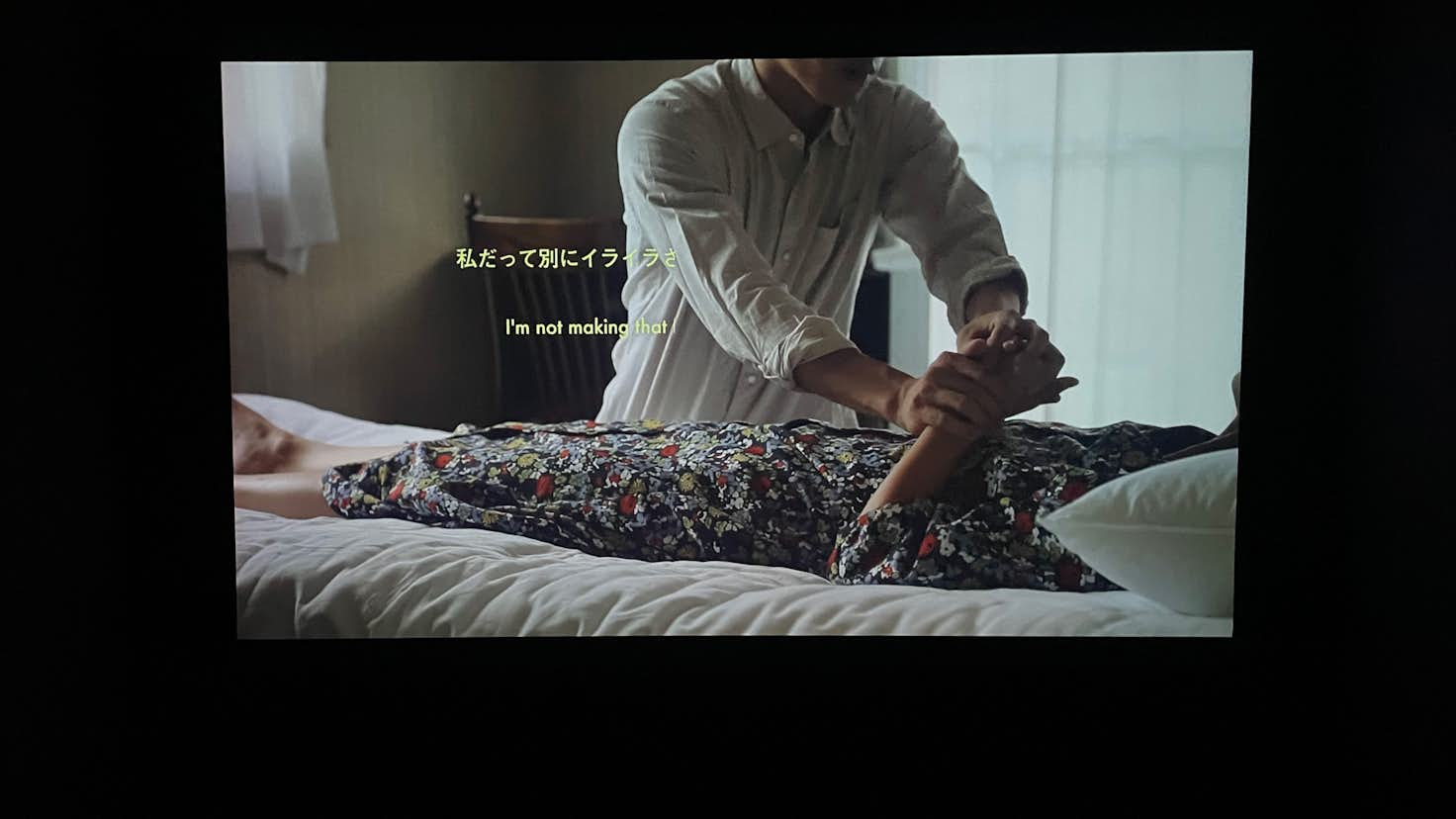
百瀬文「口を寄せる」(十和田市現代美術館/2022年12月10日~2023年6月4日)

本展にあわせて制作された新作《声優のためのエチュード》(2022)が鮮烈な印象を残した。前作《Flos Pavonis》(2021)は政治的メッセージの強い短編映画仕立ての映像作品だったが、打って変わって《声優のためのエチュード》は圧縮度の高いサウンド・インスタレーションである。その内容は、「これは私/僕の声です」「これは私/僕の声ではない」という数種の台詞を読み上げる女性の声優の声が、ランプの明滅と同期しながら真っ暗な展示室に響き渡るというもの。それまで映像作品を数多く手掛けてきた百瀬が映像を封じた経緯も気になるところだが、振り返って考えれば、暗闇のなかに偏在する声=音像を身体で受け止める経験というのも一種の映像体験と呼べるのかもしれない。もうひとつ重要なのは、本展に通底するテーマが作家がかねてより追求してきた「声」であるという点。《声優のためのエチュード》では、話者から吐き出された「声」が「私」から分離して異物となるプロセスが扱われていたようにも思える。広告、宣伝、勧誘、禁止、命令、呪詛。「声」が過剰にあふれる情報社会を生き延びるすべとして、異物としての言葉を聴取/感受する感性は今後いよいよ問われるものとなっていくだろう。
中島りか「□より外」(TALION GALLERY/5月27日~6月25日)

Courtesy of TALION GALLERY
プロジェクトスペース「脱衣所」を始動し運営するなど、近年目覚ましい活躍を見せる1995年生まれの作家による個展。長崎の隠れキリシタンの歴史についてのリサーチをベースに、オラショと呼ばれる祈りの言葉(隠れキリシタンたちが異教である仏教のお経の効果を打ち消すために用いた歌の一種)をモチーフとしたサウンド・インスタレーションや、海で壺を洗う儀式めいたシーンを撮影した映像作品などを展示。展示空間には緑の十字マーク、三角コーンといった都市環境に潜む不穏な象徴的形象と、《マリアのよごれ》(2023)のような宗教的文脈をもつ非形象とがたくみに配置され、社会的事象とスピリチュアリズムが交差するインスタレーションが展開されていた。もっとも本展の真骨頂はそうした文脈の重層性よりも、象徴の力を内側から崩さんとする内破力にあったように思える。呪いをかけることよりも祓うこと、解体することのほうが難易度が高いのだとしたら、中島の展示は破格の手法でその難事に挑んだと言えるのではないか。
伊庭靖子「伊庭靖子 個展」(MA2 GALLERY/9月9日~10月14日)

2019年に開催された個展「伊庭靖子 まなざしのあわい」(東京都美術館ギャラリーA・B・C)は伊庭の突出した技量を物語る珠玉の展示だったが、今年、MA2 GALLERYで開催された本展もまた、伊庭が倦まず弛まずの探究を続けていることを再確認させる質の高い内容だった。とくに目を引いたのは、画家が近年取り組むようになった風景画の大作。制作では赤外線カメラで撮影した写真を補助手段に用いているらしく、肉眼とは異なるメカニズムの視覚像が一望して把握しがたい複雑な光景をつくり出していた。鑑賞者の目は解像度が一様でない画面の上をさまよい、「絵を見ている自分」の居場所の不確かさまでも体験することになる。いま目の前に見えている世界を自明視せず、視覚の成立過程そのものを遡行して点検すること。そのために、前提となる主体の視覚の外へと出て行くこと。このような懐疑の能力なしに芸術作品が生まれないことを、伊庭の作品は教えてくれる。





